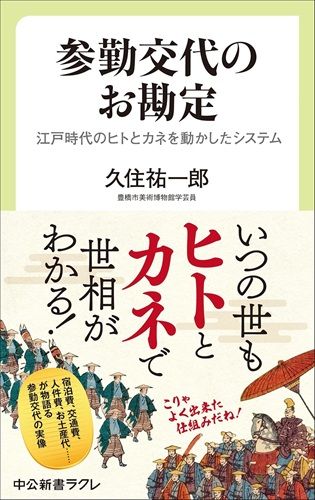臨時出費をもたらす手伝普請
では、参勤交代は藩財政を悪化させたと言えるのだろうか。
新発田藩では、元禄14年(1701)9月18日に藩士たちへ次のような通達を出している。
麻布新堀の手伝普請を務めて以降、藩財政が難渋して借金も年々増大している。その上、領内では米の不作が続いている。今後は家臣たちの手当を出すことが困難であり、来年春から5年の間は家臣から人足を出させることを免じるので、なるべく召使いを減らし、米や金を借りないように倹約しなさい。
新発田藩では元禄11年(1698)に江戸麻布新堀の手伝普請を命じられたが、それが財政悪化の原因の最たるものだと認識していた。
手伝普請は太平の世にあって主要な軍役の一つとなっていた。江戸時代前期には城郭や江戸の街づくりによるものが多かったが、中期以降は河川を対象としたものが増加した。日本列島では17世紀に耕地面積が1.5倍に増えたが、その多くは水害が発生しやすい大河川の下流域の新田開発によるものであった。
しかし、こうした大河川の治水工事は対象が複数の領主の支配地にまたがっており、個別対応が難しく、幕府が主導する公共的な事業になった。この河川の普請に大名の手伝普請があてられることになった。
代表的なものでは、寛保(かんぽう)2年(1742)に洪水が発生した関東地方諸河川の普請がある。この時は熊本藩・長州藩・津藩・岡山藩・福山藩などが手伝普請を命じられ、熊本藩は約12万7000両(121億9200万円)もの出費があった。宝暦4年(1754)から翌年にかけておこなわれた木曽三川の治水工事は薩摩藩が請け負ったが、難工事のため工事費がふくれあがり40万両(384億円)という大金になったという説がある。
手伝普請は参勤交代とは比較にならないほどの大金を用意しなければならないが、藩にそのような臨時出費に対応できるだけの蓄えはなく、多くは上方の大名貸や領内外の豪商からの借金で賄った。
また、江戸時代は地震や飢饉などの大災害が繰り返し発生した時代でもあった。新発田藩では洪水がたびたび発生し、田畑の水損が5万石を超える年もあった。被災した藩では急場を凌ぐために幕府から数千両単位の借金をすることもあり、災害対応やそれにともなう借金の返済も藩財政を圧迫した。
参勤交代は確かに道中経費だけでなく莫大な江戸での出費をもたらし、それが藩財政の中で支出の大きなウエイトを占めていたことは間違いない。
だが、直接的に藩財政を苦しめたのは、幕府から命じられる手伝普請や繰り返し発生した災害などの突発的に大金が必要となる事象であった。これらに対応するための借金は、倹約令や給与カットといった支出削減の努力を一瞬で吹き飛ばし、次第に積み重なっていくことで藩財政を長期にわたって苦しめたのである。
※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(著:久住祐一郎/中央公論新社)
幕府が大名の力を削ぐための施策であったという理解は今は昔。
最新の研究や詳細な史料をもとに、参勤交代の多面的な姿を明らかにする。
『三河吉田藩・お国入り道中記』で、三河吉田藩という一つの藩をマニアックなまでに掘り下げた著者が、経済や文化に多大な影響をおよぼした参勤交代の、巨大で豊かな全体像に迫る。