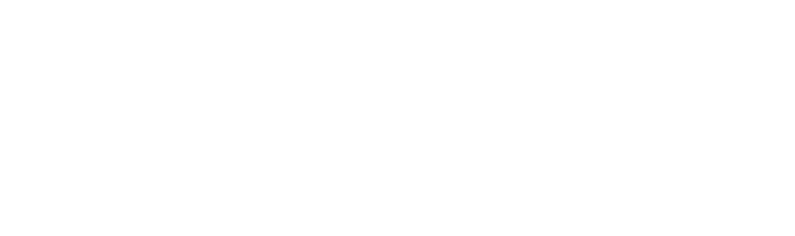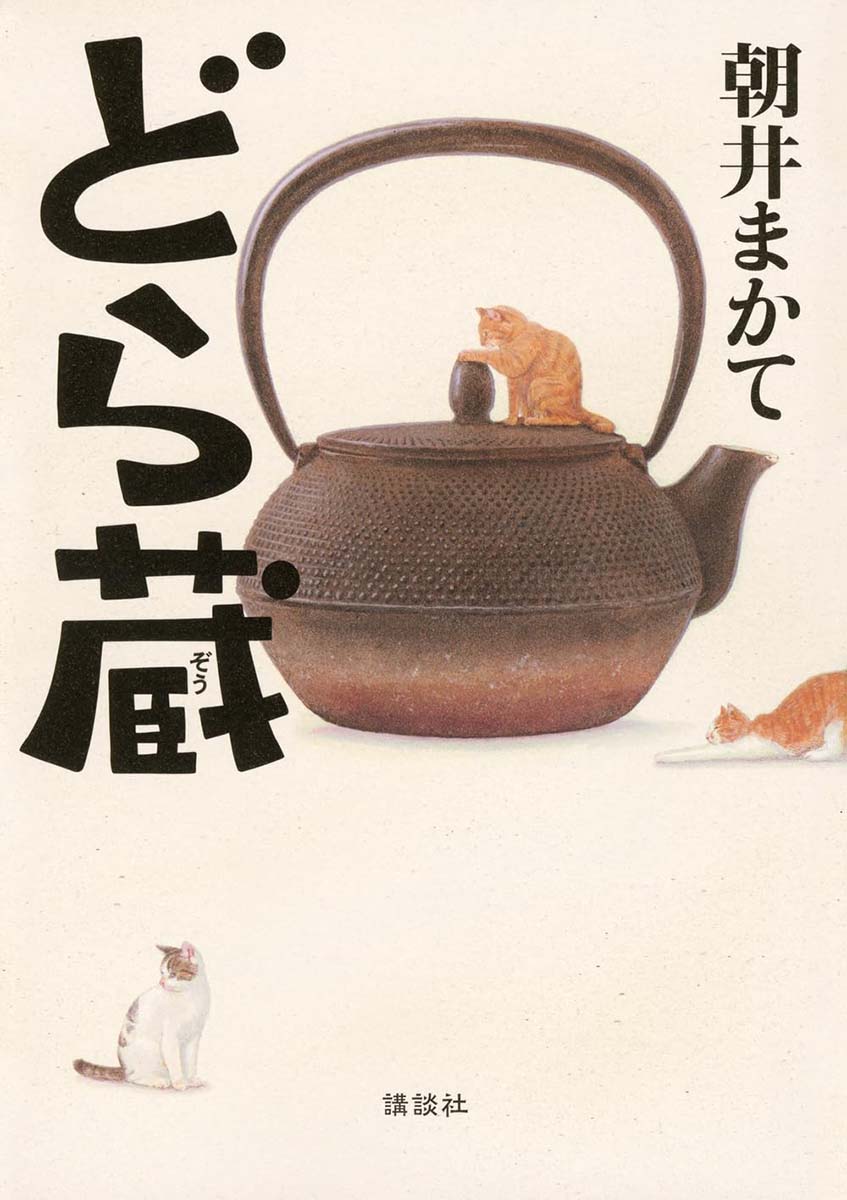真贋のあわいを描きたかった
もう一つ、骨董をテーマにするなかで私が描きたいと思ったのが「真贋のあわい(間)」にあるもの。
美術館で名品として飾られる茶碗も、もとは高麗の名もない職人が作り、海を渡って日本に来た時に、「いいじゃないか」と思った人がいて。それが名のある戦国武将だったりすると、時とともに物語が付加され、「由緒」になります。
その茶碗と、同時期に作られたほかの茶碗にはさほど違いはないかもしれない。誰かによって見出されること、つまり人間によって運命が変わるんですね。
本物か贋物か、それをめぐる話もドラマチックで面白い。でも本作は善悪、白黒、真贋で分けて争うドラマとは異なるものです。白黒、善悪の「あわい」があるから、人は息ができる。〇か×かのジャッジしかない世の中は、息苦しく生きづらいと思うから。
主人公は、ひょんなことから手に入れた小さな壺を、その真贋はともかく愛して、大事にする。大事にされた壺はめぐりめぐって、彼の支えになってくれます。私自身、好きであるかどうかがいちばん大切。時には失敗もしながら磨いていくのが、目利きのセンスというものなのでしょう。
作中、「倅(せがれ)には『その歳で物を増やしてどうする』と叱られる」と笑いながら、骨董市で楽しそうに茶碗を選ぶ老夫婦が出てきます。「老い仕舞いを始めたら本当に老けちゃう」「貯えなんぞ下手に残したって子の為にならない」という二人の台詞に、うなずいてくださる読者もいらっしゃるのでは。
本作はフィクションですが、設定は江戸時代後期、大河ドラマの『べらぼう』のあと。町人文化が爛熟した時代を背景としているので、読者に馴染みのある人物も登場します。歴史上の重要な事件も起き、現代に通ずる世相、人情にも触れることになりました。企まずして。(笑)
自己肯定感がやたらと高いどらちゃんと一緒に、目利きの旅を楽しんでくだされば嬉しいです。