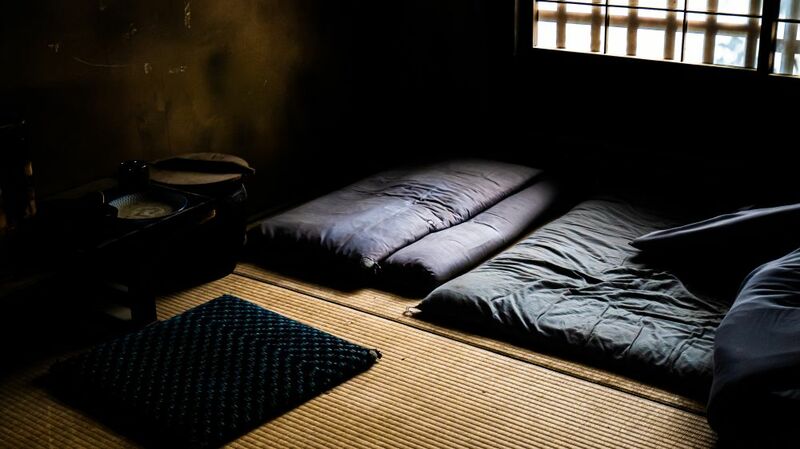日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK総合、日曜午後8時ほか)。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「梅毒」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし!
梅毒でこの世を去ったきよ
前々回のドラマでは歌麿の妻・きよが瘡毒(梅毒)でこの世を去りました。
歌麿・きよの夫婦生活が描かれたのはたった3話。
二人の幸せな時間があまりに短く終わってしまったのは悲しい限りでしたが、今回はその死の原因となった梅毒について記してみたいと思います。
20年くらい前でしょうか、東大内の情報学環に籍を置いていたとき、同僚の教員の勧めで、アフリカのマラウイ共和国を対象としたドキュメント映画を見たことがありました。
マラウイには世界第9位となる、九州の80%ほどの広さをもつ湖・マラウイ湖(世界遺産に認定されている)があって、ここには多くの淡水魚が生息しています。
とくにナマズは淡白な白身魚として食用に適していて、加工してイギリスに輸出され、フィッシュ&チップスの原材料になっています。