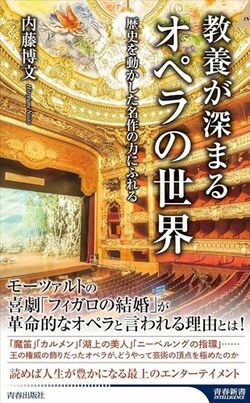「カルメン」で描かれたスペイン的エキゾチズム
「カルメン」の時代のエキゾチズムとは、鉄道交通の発達と民族文化の発見の時代がもたらしたものである。19世紀半ば以降、ヨーロッパでは鉄道建設が進み、フランスではとくに1950年代から1960年代、ナポレオン3世の帝政時代に鉄道網は急速に普及していった。それまで見かけなかった南仏のワインやチーズも、やすやすとパリに流入していた。
こうしてフランス域内の鉄道網が形成されていくと、スペインはそんなに遠い国ではなくなってくる。それまでフランスとスペインはピレネー山脈によって分断されていたが、鉄道網の発達によって、互いの実像が少しは見えてくるようになったのだ。しかも、ナポレオンの時代、フランスのスペイン侵略によって、フランス人は多少なりともスペインを知るようになってもいた。
その先にあったのが、民族文化の発見である。フランス革命以降、ヨーロッパの各国、各地域で高まっていたのはナショナリズムである。ナショナリズムが盛り上がっていくほど、人は「民族」の違い、「民族文化」の多様性に気づく。この時期、ロンドンやパリでは万博が開催されはじめていたが、万博は民族文化の品評会の一面を持っていた。
19世紀、国民国家の形成に民族固有の文化発見は重要だった。ゆえにドイツではグリム兄弟が登場、ドイツの民話を蒐集(しゅうしゅう)していった。ワーグナーもまた、ゲルマン民族に関わる神話、民話を集め、掘り下げ、オペラ化していった。その集大成が、大曲「ニーベルングの指環」となる。
この鉄道の発達、民族というものの認識が進むにつれ、フランスでもスペイン人、スペイン文化が半ば幻想、半ばリアルな形でわかってくる。それが、「カルメン」で描かれたスペイン的なエキゾチズムである。
「カルメン」は、スペインのセビリアを舞台にしたオペラだ。セビリアを舞台にしたオペラといえば、これまでにモーツァルトの「フィガロの結婚」、ロッシーニの「セビリアの理髪師」、ベートーヴェンの「フィデリオ」などの有名作がある。いずれも「カルメン」よりも半世紀以上も前に上演されているが、モーツァルトのセビリアもベートーヴェンのセビリアも、国籍色に乏しい。セビリアは、ただの記号のようなもので、「フィガロの結婚」にしろ「セビリアの理髪師」にしろ、スペイン情緒はどこにもない。あるとすれば、イタリア情緒やウィーン情緒の類いだろう。
ところが一転、ビゼーの「カルメン」にはスペイン情緒とおぼしきエキゾチズムが満載となっているのだ。それは、時代の移り変わりのなせる業なのだ。ちなみに高名な「ハバネラ」については、じつはもともとはキューバの民族舞曲様式で、スペインに持ち込まれたものであるのだが、ビゼーはこれをスペインの民族舞曲と勘違いしたらしい。