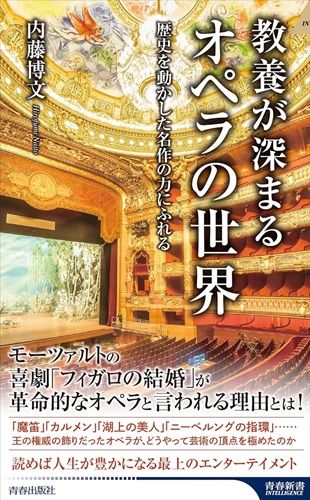フランス・オペラの反撃の尖兵
フランスにおける「カルメン」の登場は、1870年からはじまった対プロイセンとの戦争(普仏戦争)と関係がありそうだ。この戦争にフランスは完敗を喫し、その反省から近代フランスの音楽熱は湧き起こってくる。
対プロイセン戦争の敗北は、フランスにとってじつに屈辱的であった。皇帝ナポレオン3世は捕虜となって、フランスの栄光を台無しにしたし、アルザス・ロレーヌ地方を割譲しなければならなかった。
そもそも、フランスは9世紀に成立してのち、ドイツ勢力に単独で負けたことがない。ルイ14世の戦争にせよ、諸国、諸侯の連合により押し込められたわけだし、ナポレオンだって連合国に負けたようなものだ。けれども、対プロイセン戦はプロイセン一国に敗北したに等しく、しかもプロイセンは格下だった。
対プロイセン戦の敗北は、フランスの住人にドイツに対する復讐の感情をかきたてた。それが第一次大戦の遠因の一つになるが、対プロイセン戦の敗北はフランス人に自国の文化を見直させる一つの機会にもなった。フランス人なら、フランスの文化に大きく寄与しなければならないという意識が芽生えてきたといっていい。
フランスではこれを機会に、1971年に国民音楽協会が設立されている。それは、ドイツに負けない正統な器楽音楽をフランスでも創造することを目的とした組織である。
フランスにはルイ14世の時代の17世紀、王立音楽アカデミーが設置され、18世紀の革命期には国立音楽学院が始動している。フランスには音楽を育てようという歴史があったのだが、対プロイセン戦の敗北を機に、その見直し・強化がなされたのだ。
実際、国民音楽協会はフランスの交響曲や器楽曲の発展に寄与しているのだが、オペラ作曲家も奮起させたようだ。そのはじまりが、ビゼーの「カルメン」となっていたのだ。「カルメン」は、フランス・オペラの反撃の尖兵(せんぺい)だったのだ。
※本稿は、『教養が深まるオペラの世界』(青春出版社)の一部を再編集したものです。
『教養が深まるオペラの世界』(著:内藤博文/青春出版社)
ヨーロッパ最高の娯楽であり教養であるオペラとはどういうものか?
日本人に人気の『フィガロの結婚』をはじめ、オペラの主要作品を、その背景にある世界史の流れも踏まえて、わかりやすく解説。
オペラ初心者でも、オペラ愛好者であっても、その面白さ、奥深さを堪能できる一冊。