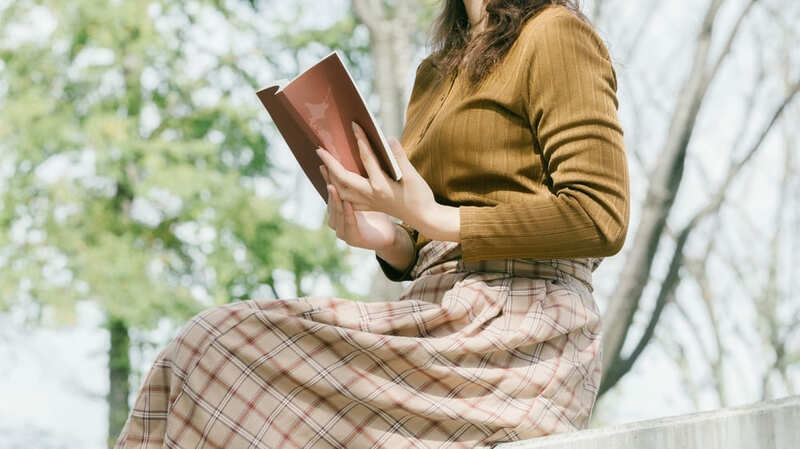「仕事に向き合おうとしてもうまくいかない」「上司が何を考えているのかわからない」など、働く上での悩みや不安は、いくつになっても尽きないもの。このような悩みについて、関西テレビや国際交流基金での勤務経験を持つ神戸学院大学現代社会学部の鈴木洋仁准教授は、「社会学」に基づいて考えることで、働きやすくなるヒントが見つかると語ります。そこで今回は、鈴木准教授の著書『社会人1年目の社会学』から一部を抜粋し、社会学の視点から職場のモヤモヤを解きほぐしていきます。
なぜ歴史を学ぶと仕事がうまくいくのか
新卒1年目の男性「なんか、歴史に学べ、とか、ビジネス書とかネットでもよく言われてるけど、面倒だし、意味あるの?」
鈴木准教授「たしかに、いまの日本では、高校までだと、歴史=暗記科目になりがちだから、そう思う理由もわかるよ。でも、だからこそ、あらためて歴史について考えてみない?」
「歴史を学ぶ意味がわからない」「テストのための暗記でしょ?」そんなふうに思っている人は少なくありません。しかし、歴史の本質は“物語”を楽しみながら、過去の出来事の「なぜ?」を考えることにあります。
「歴史は繰り返す」とよく言われますが、重要なのは「この時こういう人がこうしていたら、こうなった」という因果関係や理屈、つながりの読み解きです。乱暴に言えば、細かい名前も年代も、どうでもいい。でも、だとしたら、「歴史」ではなくて論理学で十分かもしれない。いったい、どこに「歴史」を学ぶ意味があるのでしょうか?