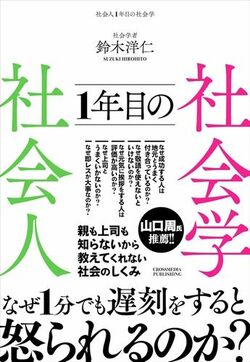「もし、信長がこうしていたら……」と考えてみる
ここで登場するのが「統計的因果推論」です。過去のデータや事例をもとに「何が原因で、何が結果か」を論理的・統計的に推測する手法です。たとえば、あなたの職場で、新しいキャンペーンを打ったら売上が伸びた、としましょう。でも、その売上増が本当にキャンペーンの効果なのか、他の要因(季節や競合他社の動きなど)が関係していないかを見極めなければなりません。原因と結果の関係=因果を、予想する=推論、というわけです。さらにそこに「統計的」=データを入れるのです。
織田信長は、誰もが知っています。彼が天下統一に迫った背景には、家臣団の統率や新しい技術の導入、敵対勢力の分断など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
「もしここで信長が別の選択をしていたら、どうなっていたか?」と考えること自体が、現代のビジネスで「この施策が成功したのはなぜか?」「他に影響した要因は?」と考える姿勢に直結します。
歴史を学ぶことは、まさにこの「因果推論」の訓練です。歴史上の出来事を「単なる出来事の羅列」ではなく、「なぜそうなったのか」「何が原因でどんな結果につながったのか」と物語として考えることで、ビジネスにも応用できる「仮説思考」や「パターン認識力」が養われます。
統計的因果推論では、「AならばB」という規則性をデータから導き出し、未来の意思決定や戦略立案に役立てます。ビジネスの現場で「これまでこういう場合が多かったから、今回もこうなる可能性が高い」と考えるのは、まさに歴史的な因果関係をビジネスに応用している例です。