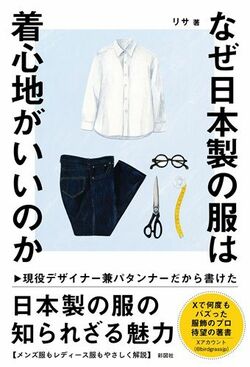貝ボタンの名産地・海南市と焼津市
温暖な海に生息している貝は、原貝の状態で日本に輸入されました。それが日本国内の産地に届くと、職人の手によって「加工」「成形」「研磨」され、ボタンに仕上げられていきました。中でも和歌山県海南市と静岡県焼津市は、高い技術で知られた貝ボタンの一大産地でした。
海南市も焼津市も、森林資源と海産資源が豊富な地域です。工芸品の原材料に恵まれており、古くから漆器や木工品などが盛んにつくられていました。職人技術が蓄積されており、特に手磨きによる研磨や穴あけ加工の技術が高く評価されていました。その技術が貝細工にも応用され、ボタン製造へと発展していくこととなります。
海南市は生産技術の高さに加え、立地の良さも強みでした。大阪・堺にも近く、ボタンの原材料や製品の輸送に適していました。1950年代にはピークを迎え、日本全国の貝ボタン需要を支える中心地となりました。
一方、焼津市は古くから遠洋漁業が盛んで、港湾都市として発展してきた町です。南洋航路の拠点として発展し、特に戦後はパラオ、ミクロネシア、インドネシアなどから貝(白蝶貝、黒蝶貝)を大量に輸入する港として機能しました。
1950年頃からは、本格的に貝ボタン産業が盛んになります。原料輸入と一次加工を行う拠点として焼津市は発展し、原料を全国のボタン工場へと供給していきました。
高度経済成長期には、輸入した原貝をスライスする荒加工の専門工場が、焼津市に林立します。加工後は海南市をはじめ、他の産地に送られ、最終製品化されるという分業体制が確立しました。
焼津市は駿河湾に面し、水深が深く大型船の寄港が可能だったため、貝の輸入港として非常に有利な位置にあります。また同地には、漁業従事者や加工業者のノウハウが豊富です。そうした、その土地ながらの豊富な知識も活かしながら、産業として発展していきました。