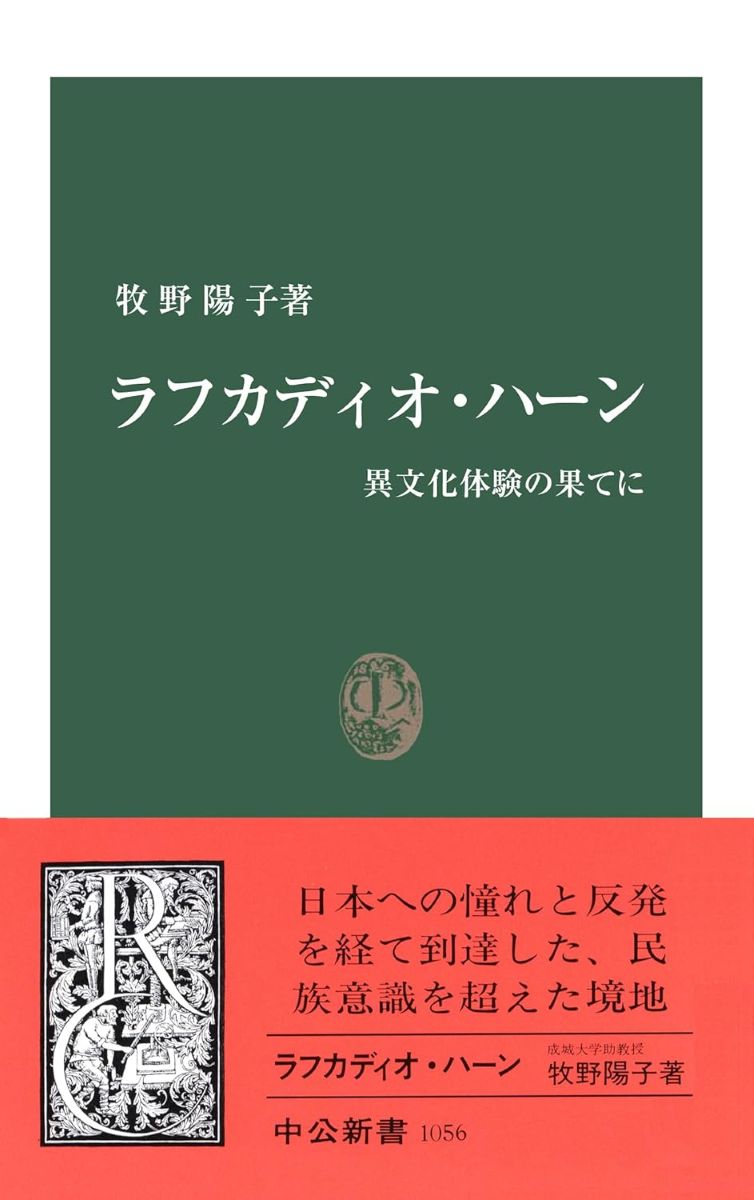異人見物に集まる村人たち
周辺の様子の変化は紀行作家らしい的確な目で観察されている。最初はどんな小さな村にも立派な仏教の寺が必ずあり、仏陀や菩薩の像が里程標のように正確に距離を刻みながら路傍に立っていた。
しかし日をへて、山高い西の奥地へと道が進むにつれて、寺の数は少なくなり、たまにあっても貧弱で小さい。路傍の石像もめったに見られない。そのかわりに、お宮と鳥居が大きく立派になってきて、神道の象徴が目につくようになる。
方言が著しく、同行の真鍋晃にも言葉がわからなくなる。家の造りもこれまでの田舎の家とは違う。農民の顔色もずっと黒い。かぶっている笠も風変わりだ。
やがて、道が突然下りになったと思ったら、視界が開け、谷間に「古い広重の画集の中にでも出てきそうな」村が見えてきた。それが伯耆(ほうき) の国、上市(うわいち)だった。
俥が小さく静かな宿屋の前で停まると、迎えに出た主は、たいそうな老人だった。ほとんど女と子供ばかりの無口でおとなしい村人たちが、異人見物とばかり俥のまわりに集まってきて、おどおどと微笑みながら、いかにも感心した風でハーンを見つめる。
ハーンはその宿に泊まることにした。古ぼけた外観に比べて家の中は実に気持ちよく清潔に整えられており、人々も親切で礼儀正しかった。
ハーンに、日本の農民を「野蛮な原住民」(イザベラ・バード『日本奥地紀行』)と見下ろすような当時の西洋人にありがちな偏見がなかったことは確かである。
だが、出雲を舞台とする連作スケッチの第一番目のこの「盆踊り」が、桃源郷文学の伝統的手法で書かれているということもまた明らかだろう。
上市に到着したハーンを出迎えるのが老人と女と子供ばかりというのも象徴的である。現実社会の代表たる成人男子の姿はそぐわないと思ってハーンは描写から落としたにちがいない。
そしてさらに、この古風な地方ではまだ旧暦を用いていたという点も、当時としてはめずらしくないことだが、いかにも文明から隔絶した感があって、大いに気にいったはずだ
※本稿は、『ラフカディオ・ハーン 異文化体験の果てに』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『ラフカディオ・ハーン 異文化体験の果てに』(著:牧野陽子/中央公論新社)
他のお雇い外国人と異なり、帰るべき故郷を持たないラフカディオ・ハーン。
ハーンが神戸、東京と移り住むうちに、日本批判へ転ずることなく、次第に国家・民族意識を超越し、垣根のない文化の本質を目ざしてゆく様子を描く。