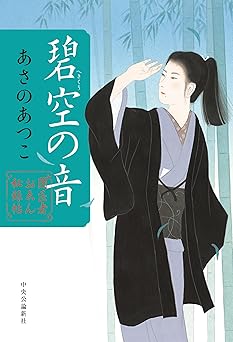「それは、先生のお仕事だからでしょ。あたしに逢いに来るわけじゃありませんよね。いわば、美濃屋と交わした約定です。あたしのためじゃないでしょ」
「まあまあ、何て屁理屈をお言いだろうね。つまり、お小夜さんは、お小夜さんのためにだけ、ここに来いと言ってるわけですか」
「お願いしてるんです。お頼みしているんですよ、先生」
お小夜の腕がおゑんの腰に回る。
「先生を誰にも渡したくないの。あたしだけを見てほしい。でも……無理でしょ。先生には、あたしよりもっと大切な人がいるのですもんね」
おゑんもお小夜の身体を抱いた。柔らかだ。その柔らかさの底に硬い芯がある。
「大切な人というのは、誰のことです」
「……わかりません。でも、あたしでないことだけは確か。きっと……」
「きっと?」
「誰でもないんだわ。現の誰でもない。いえ、違いますね。反対だわ。誰でもないのじゃなくて、現に生きる誰も彼もが大切なんですよね、先生って。先生の許にやってくる女たち、生きるための最後の手立てとして、先生に縋ってくる女たちがね」
お小夜の指が動き、おゑんの羽織の紐を解いていく。
「先生……」
黒羽織が足元に落ちた。
「一時でいいです。ずっと想ってくださいなんて贅沢は望まない。だから、せめて一時、あたしだけのものになって。先生、お願いします」
腰に回った腕が震えていた。背中も胸も全身が震えていた。
「わかりましたよ、お小夜さん」
「え?」
「お望み通り、お小夜さんのためにだけ、美濃屋に参りましょう。ただし」
ただし何ですか――問うように、お小夜が顎を上げる。
「抱きませんよ」
お小夜の顎の先が、ひくりと動いた。
「ここで、この座敷で、いいえ吉原のどこであっても、おまえさんを抱いたりしないよ」
お小夜が僅かに後退りした。腕が離れる。それだけのことなのに、身体の熱が一気に奪われた気がした。背中から冷えていく。
「それは、どういう意味です。あたしが遊女だから抱けないと……」
「そうですね。ええ、その通りですよ。吉原にいる限り、お小夜さんは、花魁安芸の面をつけていなくちゃならない。お小夜に戻っても、それは一時のこと」
「一時で構いません」
おゑんを遮るように、お小夜が叫んだ。
「一時でいいって、それ以上の贅沢は望まないって、あたし、言ったじゃないですか」
「一時でお仕舞いにするつもりかい」
物言いを荒くする。お小夜が瞬きをした。黒い眸の中で何かが揺らめいている。
「おまえさんは、ほんの一時だけお小夜に戻り、あたしと睦み合う。本当にそんなことを望んでいるのかい」
お小夜の眉が顰められる。美しい顔が歪んだ。
「先生……先生の言っていることがわかりません。まるで、わからない」
「お小夜さん」
おゑんは腕を伸ばし、お小夜の肩を掴んだ。抱き寄せる。
「わからないなら、考えな。途中で諦めるんじゃなくて、考えるんだよ。あたしはね、考え続けているよ。お小夜さんとの未来(さき)をね」
「未来」
「そうさ。安芸じゃなく、素のお小夜に戻って、あたしと生きていく未来を考えてみちゃあどうだい。抱くとか抱かれるとかじゃない。そんなちっぽけなことじゃなくて、おまえさんが誰とどう生きて、どう老いて、どう死にたいのか。そこんとこだよ」
「そんなこと、考えたこと……なかった。一度も……」
喘ぐように、お小夜が呟く。吉原で、自分の未来に、行く末に、本気で思いを馳せる女などほとんどいないだろう。いや、男も同じかもしれない。
刹那、刹那を生きて、刹那に死んでいく。
「吉原から離れて生きる明日なんて、考えたことなかった。本当に一度もなかった」
「じゃ、考えてごらんな。本気でね。お小夜さん」
「はい」
「悔しいけれど、あたしにはおまえさんを解き放つ力はない。吉原って鳥籠から外に出してやるだけの力がないんだよ。だから、自力で出ておくれな」
籠を壊し、自ら外に出るのだ。
そして、空へと飛翔する。
いつまでも、囲われているわけにはいかない。
お小夜はいつか、耐えられなくなる。
「先生、あたし、もしかしたら落籍(ひか)されるかもしれません。さる大店の旦那さまが、是非にと望んでくれました。うちの旦那さまはまだ、お返事をしていないのですけれど」
安芸を落籍すとなると、とてつもない費えが掛かる。それを出せるだけの大店、おそらく江戸でも五指に入る店の主人なのだろう。並の商人に手が届く女ではない。
「なるほどね。じゃあ、美濃屋さんは渋っているわけだね」
渋るというより悩んでいるのだろう。安芸がいなくなれば、美濃屋は大輪の花を失う。「ここが美濃屋だ。あの安芸がいる妓楼だぞ」と人の口に上らなくなる。遊女屋としての格が下がる。けれど、総籬の構えだけは保たなければならない。なかなかに難儀なことだろう。
それだけではない。安芸は吉原最後の呼出し昼三だと言われている。安芸の後、その位に相応しい花魁はもう出てこないとみなされているのだ。
大輪の花を失うのは美濃屋一軒に留まらず、吉原全ての失となる。
そういう諸々の憂慮を安芸の身請け金の額と照らし合わせ、天秤に掛け、悩み続けている。そういったところか。美濃屋の主、久五郎には前々からすっぱりと物事を決めかね、あれこれ思い惑う悩み癖があった。遊女屋の主、亡八(ぼうはち)としては些か器足らずかもしれない。けれど、久五郎の人臭い惑い方がおゑんには好ましくも、おもしろくもあった。当の本人からすれば、おもしろがるどころの話ではなかろうが。
「その話、お小夜さんはどう思ってるんだい」
「あたしは……どちらでもいいと思っていました。花魁としていられるのも、長くてあと四、五年、いえ、三、四年ほどでしょう。囲い者として生きるのだって、それくらいのものです。飽きられたら終わりですもの。客も落籍を望む旦那さまも、あたしの若さを愛(め)でているだけです。若さなんて、すぐに擦り減ってしまうでしょう。そうなったら、あたしは羽をもがれた小鳥みたいなものかなって思ってました。でも……違うのかしら。先生、あたし、羽をもがれたりしないのでしょうか」
「だね。そんな柔な羽じゃないはずだよ。それに小鳥でもないだろう。鷹か鷲か梟(ふくろう)か。どれにしても、鋭い嘴(くちばし)と鉤爪を持っているはずさ」
ふふと、お小夜が笑う。媚も誘いもない。いかにも楽しげな笑みだった。
(この章、続く)