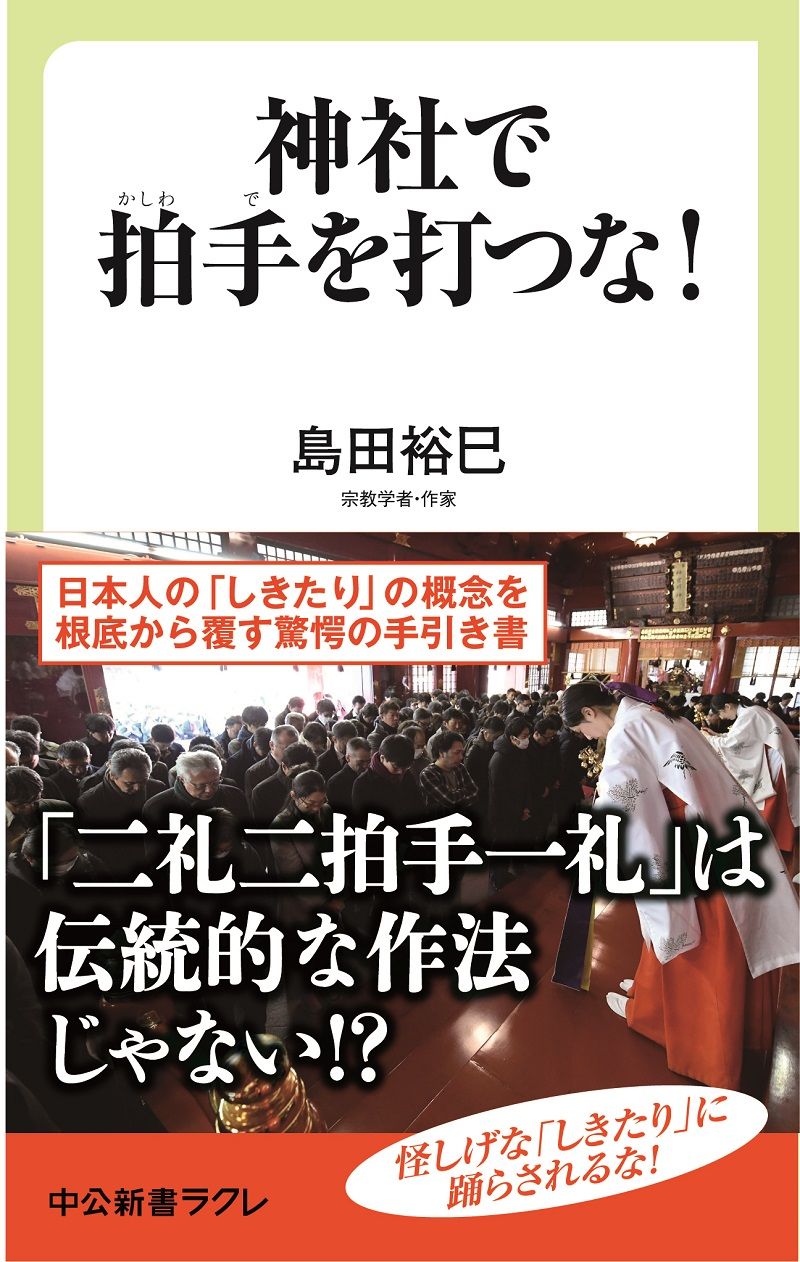人々を縛ってきた家のしきたり
しかし、この説は、山の神や田の神が登場するように、あくまで農家の生活をベースにしたものであり、都会では成り立たない。戦後は、都市へ出る人間が大幅に増え、都市的な生活が中心になってきた。
都市に成立した家に住むのは、主に企業などに雇われた人間であり、家は、農家とは異なり、経済的な活動の場とはなっていない。その分、家を是非とも存続させていかなければならないという意識は希薄で、事実、家は長くは続かなくなった。
となると、家のしきたりもなくなる。結婚した嫁が夫の家に入り、その家のしきたりを学んでいかなければならないなどということは、もうなくなった。以前はそれを教えた夫の両親と同居しているわけではないからである。
家のしきたりが力を持たなくなったことは大きい。というのも、それがもっとも、人々の生活を縛ってきたものだからである。それぞれの家に育った子どもたちは、家のしきたりを守るよう仕向けられることで、しきたり全般を受け入れることを学んでいった。
私たち日本人は、今やしきたりということそのものから解放されつつあるのではないだろうか。しきたりは、今までも見てきたように、村や地域社会、あるいは組織といった特定の共同体によって守られてきたものである。ところが、そうした共同体が現代では失われてしまっているのである。