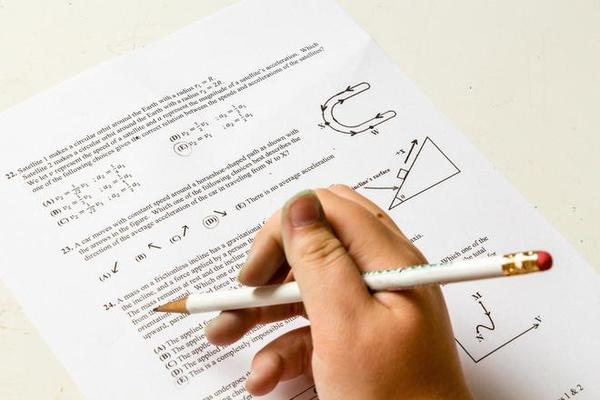緊急事態宣言が首都圏や都市部にふたたび発令されるなか、大学入試の「共通テスト」は予定通り行われる見込みだ。今回が初めてとなる共通テストに関しては、筆記試験や民間英語検定の導入を目指していたものの、教育機会の平等や均等から見れば「不公平」と主張する意見が強く、想定した試験内容を盛り込めないまま実施に至ることとなった。一方アメリカやフランス、日本のアカデミズムに身を置いた経済学者の橘木俊詔氏は「繕われた公平さに意味などない」と指摘する。進学率が5割を超え、もはやエリートのためのものではなくなった大学で、教育は、教授は、そして学生はどうあるべきか。入試本番のこの時期だからこそ、改めて考えてみたい。
※本稿は橘木俊詔『大学はどこまで「公平」であるべきか』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
※本稿は橘木俊詔『大学はどこまで「公平」であるべきか』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
50%を超えた大学進学率だが
文部科学省の統計『令和元年度学校基本調査』によると、2019年の日本人の大学(学部)進学率は53・7%。短大を含めれば、その進学率は58・1%、ほぼ6割にまで達していることが分かる。
1980年代の大学進学率は30%前後に留まっていた。しかし平成に入ってから、女子学生の増加とともに右肩上がりで上昇。90年代後半には大学・短大進学率の合計が50%台に突入し、大きく下がることなく今に至っている。
都道府県別で見ると、1位の京都府が65・87%、2位の東京都が65・13%、3位の兵庫県は60・90%、4位神奈川県60・70%であるのに対して、44位が鳥取県の43・31%、45位が鹿児島県の43・28%、46位は山口県43・06%、47 位の沖縄県40・19%となっている。
なお厚生労働省の『賃金構造基本統計調査の統計データ(2019年度)』によれば、都道府県別年収ランキングのトップテン内に京都府、東京都、兵庫県、神奈川県がすべて入っている。逆に、ワーストテンのなかには鳥取県、鹿児島県、沖縄県が入っている。
このデータを踏まえれば、県民所得の高い府県と低い府県とで大学進学率にはある程度の相関関係があり、大学進学率は家計所得によって左右されがちと言えるのかもしれない。
しかし『大学はどこまで「公平」であるべきか』でも詳しく記したが、昨今の入試改革では、こうした意味合いでの「公平さ」はほとんど語られることがないまま、ここまで進んできた(そして今も触れられていない)印象が強いことはここに追記しておく。