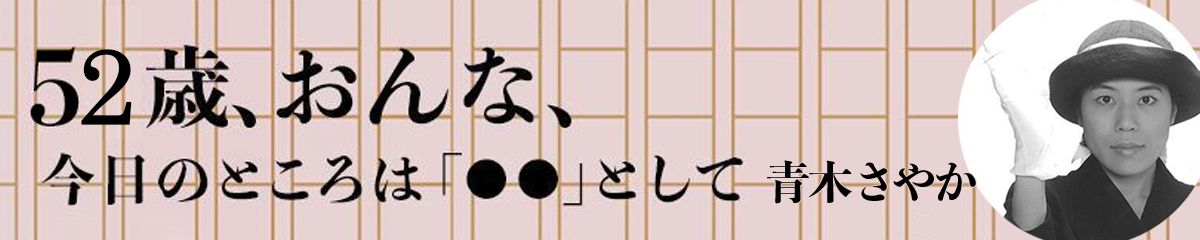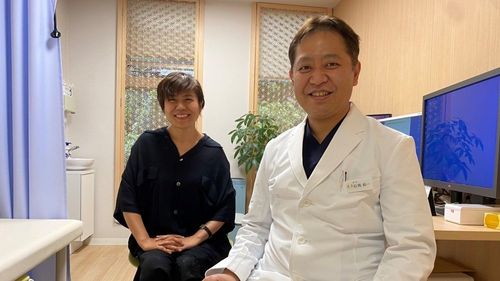がんだというのは現実らしい。倒れこみたい気分だが、まず考えなくてはならないのは、ひどく現実的なことばかりだった。
入院中、娘のことをどうするか、お金はどれくらいかかるのか、復帰はいつできるのか、肺など切って舞台など出られるのか。
わからない。
とても不安だったが、手術をしていただくことになった、当時東大病院にいらした似鳥先生や周りの方たちにより、不安はある程度解消された。
何をしても楽しくない
入院が決まり、報告しなくてはならない人への報告を済ませて一息ついた。これで、
娘のこともその後の仕事のことも一旦安心、になった時、わたしは泣きたくなった。
誰かにもたれかかって泣きたくなった。恋人がいい。でも相手がいなかったから1人で
車の運転席で堰を切ったように泣いた。
あとにもさきにも、がんのことで泣いたのはこの時だけだ。

手術をするまでの間、毎日怖かった。心ここにあらずで娘とごはんを食べた。
自分の病気を、ネットで調べた。生存率が書いてあったり、闘病記が書いてあったりした。それは、少なくともわたしの心を明るくするものではなかったから、
わたしはネットで病気を調べるのをその日でやめた。
いつもみる景色は、いつもと違ってみえた。どこか違う世界にきたように思えた。
何をしていたって楽しめなくて、受験前みたいな気分だった。
それでも、入院前に小川菜摘さんが連れて行ってくださったお寿司は美味しかったし、
カメラを向けられれば笑顔ができた。がんになっても街にでれば「健康そのものね」と
言っていただくことは多く、見た目ではわからないものだ、と自分をみて思った。
よかれと思ってアドバイスをくれる人はいたが、耳に入ってこなかった。その相手が、気遣いが足りないとか、それは必要ないことだとか、そりゃ理由付けはいくらでもできるが、そうじゃない。
結局のところなかったのは「私自身の余裕」だった。余裕さえあれば、どんなことを言われてもぜんぶぜんぶ、笑っていられるのに。
わたしは、病気になって、いつにも増して余裕をなくしていた。
入院当日、わたしは自分で車を運転して1人で病院へ向かった。
青木さやかさんの公式HP
https://z0z0.jp/sayakaaoki/