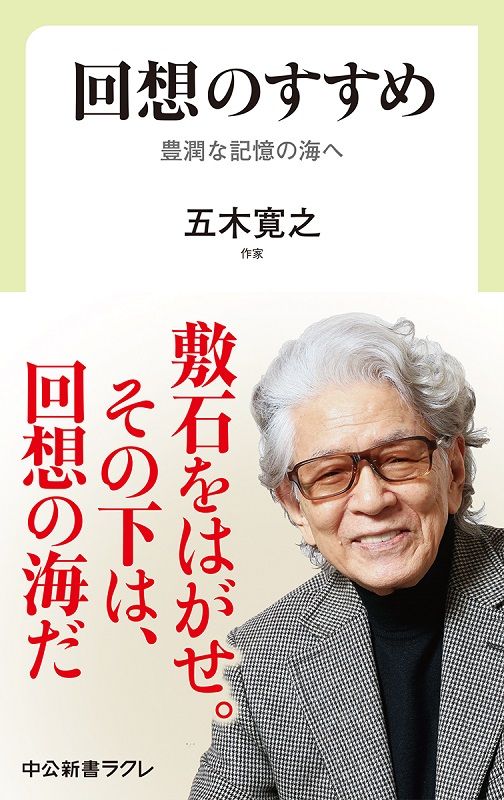責任、ということを重く考えていた人
いちど鈴木いづみが自殺したときの話を森瑤子にしたとき、彼女は耳を手でおさえるようにして、
「やめてください。聞きたくない」
と、叫ぶように言った。
「なぜ子供をおいて、そんなことができるの」
森瑤子という人は、責任、ということを重く考えていた人だったような気がする。世の中に出ていくために自分が演じた役割りを、最後まで演じなければならないと、ある時から覚悟をきめていたのだろう。
森瑤子には、どこかシベリアの大地に生きるロシアの農婦のような骨太さがあった。世間に出るために演じた役は、どんなに大変でも最後まできちんと演じ切らなければ、という責任感が彼女の生き方を支えていたのではあるまいか。
彼女は作家としての義務をはたすと同時に、妻として、母としてもその責任をまっとうしようと心に決めていたようにも見えた。
あるとき、彼女の自宅に招かれてディナーをごちそうになった晩、私はいつもの通りトックリのセーターにツイードのジャケットという気楽な格好で出かけた。
その席にもう一人べつの男性客がいた。その人がきちんとした服装で席につくのを見て、私は大いに恥じ入ったものだった。ディナーに招待されるということに慣れていない田舎者である自分に首をすくめる気がしたのだ。
しかし、そんな私を森瑤子はしきりに気をつかって、カジュアルな食事の会に持っていこうと苦心してくれていた。そこには時代を駆け抜けるランナーとしての森瑤子と、まったく別の、田舎のオバさんがいたのである。
しかし、いま思い出すと、あのガリガリという氷の塊を噛みくだく音だけが鮮明に耳に残っている。それは忘れられない音だった。