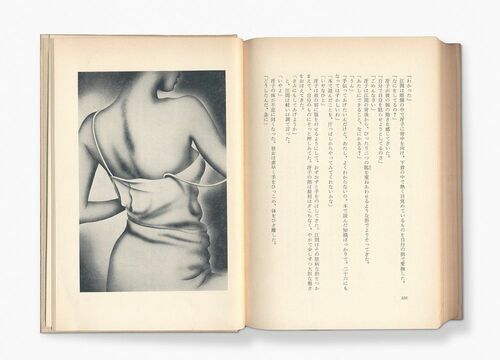スタッフ全員から完全ボイコット
『幻の女』の公演が終って、しばらくして再び深夜のパスタンで会ったとき、石岡さんはまるで髪を逆立てたように怒っていた。
「五木さんがこれほど薄情な人だとは思ってもみなかった。いまはあの仕事を引き受けたことを後悔してる」
「舞台を観にいかなかったことかい」
「それはかまわない。それより途中で応援にきてくれなかったこと」
「なにがあったんだい」
「この国ではアートディレクターという仕事が確立されていないんだよね。舞台美術を担当します、といったって、ほとんど相手にされなかったんだから」
彼女の話では関係者一同から全く無視されたような状況だったらしい。どこかの小娘が横から割りこんできてセットから衣装、ライティングにまで口を出すとはどういうことか、と大道具、小道具などのスタッフ全員から完全ボイコットをくらったのだという。
たしかに当時はデザイナーとか、イラストレーターとか、そういう仕事の分野が、まだ社会一般に確立されていない時代だったのである。資生堂やパルコの広告を手伝っている小娘、ぐらいにしか思われていなかったのだろう。
「だれも協力してくれない。そこ、どいた、どいた、なんて大道具の人にお尻たたかれて、邪魔者あつかいだったんだから」
「ふーん」
「この国って駄目だね。わたし、つくづくそう思う」
話によれば舞台に関して一切の雑務を彼女一人でやったのだそうだ。
「夜中に泣きながら雑巾もって床をふいてたんだよ。わかる? その口惜しさが」
「ごめん」
「ごめんじゃないよ。どうしてちゃんとバックアップしてくれなかったのよ」
髪を逆立てて、と書いたが、ふだんから髪が逆立っているような人なのだ。そのときは浅黒い頬に涙が伝うのを複雑な思いで見た。
彼女が泣いたのは、単に一劇団とのトラブルのせいではなかった、と今ではわかる。それは、この国の表現や創造の仕事に対するどうしようもない前近代性についての哀しみだったのではあるまいか。