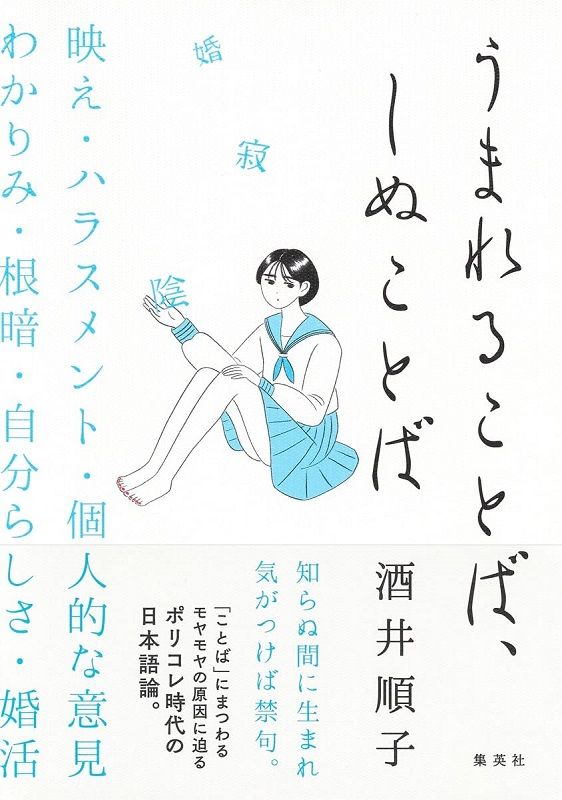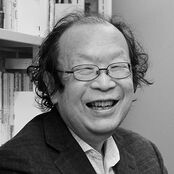言葉の乱れではなく変化だから、しょうがない
金田一 「終了します」でいいですよね。シンプルといえば、戦後すぐのころに「敬語を使うのをやめよう」という運動があったんですよ。戦前まで使っていた「おいしゅうございます」という表現ではなくて「おいしいです」。「あこうございます」じゃなくて「赤いです」でいい。「いらっしゃる」も「召し上がる」もやめようよ、と。
酒井 その運動には、どんな方たちがかかわっていたのですか?
金田一 国立国語研究所とか作家の山本有三さんとか。うちの父もそうですね。戦前の日本語は合理的じゃない。もっとシンプルに、わかりやすい言葉を使うべきだ、と。
酒井 民主化を進めるためという意味合いもあったのでしょうか。
金田一 ええ。
酒井 そんな運動があっても、われわれはどんどん言葉の過剰包装をしたくなってくるわけですね。
金田一 そう。いくら「敬語はやめよう」と決めたところで、相手を敬いたいとか、商業的なこととなれば、余計に《もてなしたい》という気持ちが自然と出てくる。だから、こうして不思議な敬語が再び生まれてくるわけです。
酒井 最近の「させていただく」は時代の揺り戻しということなのかも。それならば、そんなに否定しなくてもいいのでしょうか。
金田一 まあ、変は変だけどね。でも言葉の乱れではなく変化だから、しょうがない。「おかしいよね」「古いほうがいいよね」と大人が思ってしまうのは、人は言葉でアイデンティティを作ってきたからです。自分が使ってきた言葉が古いとされると、自分を否定されたと思ってしまうのでしょう。
酒井 なるほど。