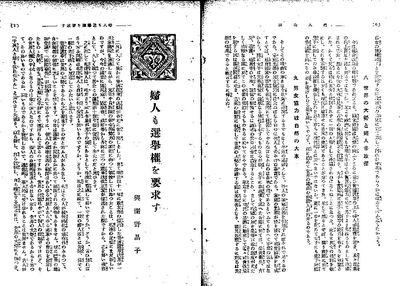納税額を標準とする選挙法の第一の不合理
国家は国民全体の勤労に由って支持されて行くものです。国家は国民全体の協力の中に生存し発達して行くものです。一旦緩急あれば義勇を以て公(即ち国家)に奉ずるのみならず、個人が日々の勤労は直接または間接に国家のために計って居るのです。
民主主義の家庭は、その家長の専檀に依って家政を決すること無く、必ず家庭の協同員たる独立の人格を持った年頃の家族と共に公平に合議して決せねばならぬ如く、国家の政治もまた国民全体の意志に依って決することが合理的な民主主義の政治である限り、或年頃に達して独立の人格を持った国民――例えば満二十五歳以上に達して、白痴で無く、六ヶ月以上一定の地に住し、現に刑罰に処せられて居ない者――こう云う意味の国民全体が衆議院議員の選挙権と被選挙権とを持って、間接または直接に国家の政治に参与することは、立憲国民に固(もと)より備った正当な権利であるのです。かくてこそ初めて国民全体が平等に参与する政治、即ち民主主義の政治と称することが許されると思います。
こう考えて来ると、従来(これまで)の納税額を標準とした選挙権の分配の如何に不公平であるかは細論せずして明白になります。従来のように直接国税十円を選挙資格とすると、国民の中から参政権を持つ者は纔(わず)かに百四十二万二千百十八人(大正六年)を数えるに過ぎず、之を今度憲政会から提出した改正案のように納税額を二円に引下げたとしても、この倍数である三百万人内外の選挙有権者を得るに止まって居ます。かような少数の人数に由って選挙された衆議院議員が国民全体の政治的代表者と云われない事は弁ずるまでもありません。
納税額を標準とする選挙法の第一の不合理はこの点にあります。それは百五十万乃至(ないし)三百万人の有産階級のみが特権的に壟断する政治であって、国民全体の政治とは如何にも云われないものです。代議政治の美名を僭した財閥的専制政治と呼ぶのが至当です。