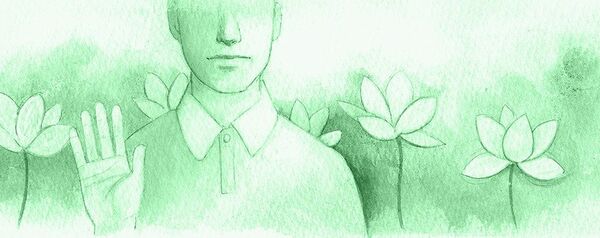
(イラスト:八木美穂子)
深夜の枕元で、暑い夏の昼下がりに、忘れていた命日に――。アレは何を知らせようとしていたのか
お盆過ぎに、警察から夫に一本の電話が
3メートルほど離れた階段近くに設置した人感センサーライトが、突然チカチカと発光した。そこには誰もいないし、虫が近くを飛んでいる様子もない。「今年はそう来たのね」と、居間のソファに一人で座りながら、地味な登場に笑みがこぼれた。 夫の3歳下の弟、エイちゃんが亡くなって3度目の命日を前にした7月29日、夜7時頃の出来事だった。
単身赴任中の夫は弟の命日を忘れていることが多いから、いつもなら私が電話で伝えるのだが、今年はすでに夫が覚えていたのを確認済み。私はそのまま夜11時頃ベッドにもぐりこんだ。
深夜1時半頃、バキバキと大きな雷のような音で目が覚める。エイちゃんだ、と思った。「忘れてないよ、大丈夫だよ」と呟きながら、また眠りについた。翌日、エイちゃんのことをもう少し話そうと夫に電話を入れた。夫は私が言葉を発する前に話し始めた。
「深夜1時半頃かな? 台所で茶碗をガチャガチャ鳴らす音がして目が覚めたよ。栄太だって思った。今日、7月30日が命日だったんだね。俺、1日間違えて命日を決めちゃった。栄太、あの時刻に一人で亡くなったのかな」
同じ日の同じタイミングに、私たちは離れた場所でそれぞれエイちゃんを感じていた。