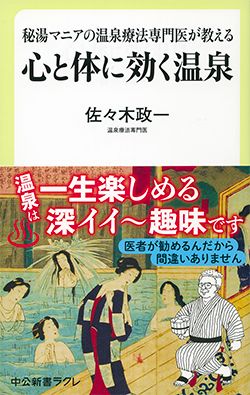●松之山温泉(新潟県十日町市松之山)
約700年前の南北朝時代、1羽の傷ついたタカが毎日同じ場所に舞い降り、終日葦の茂みに潜んでいるのを不審に思ったキコリが谷間に降りて捜したところ、滔々と熱泉が湧いており、タカはその湯に浸かり傷を癒していた。
源泉の一つは「鷹の湯」と呼ばれ、共同浴場にも「鷹の湯」の名が残る。
●鷹ノ巣温泉(新潟県岩船郡関川村)
文政2年(1819)、荒川を行き交う舟人が川辺の湧水でタカがいつも羽ばたき、水浴びをしているのを不思議に思い、確かめてみると湯が湧き出ていた。
そこで舟人が村の人たちと協力してこの周囲に石を積んで浴場を作ったのが始まりとされる。
※本稿は、『秘湯マニアの温泉療法専門医が教える 心と体に効く温泉』(中央新書ラクレ)の一部を再編集したものです。