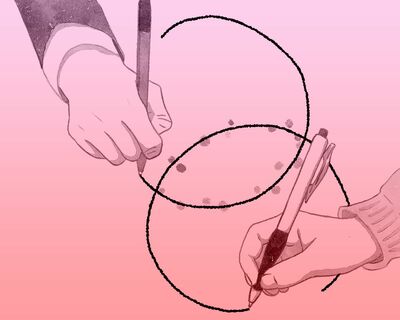退職し、人間不信のどん底にいたわたしは、五味川純平氏にひろわれた。14歳年長の氏は、大作『戦争と人間』の構想を練っておられた。
戦争の昭和を極東国際軍事裁判まで書くという大きなテーマであり、野心作であった。小説で書ききれない事件や事項を、巻末の註で補う。その仕事をやらないかと誘われた。
昭和11年に受験で上京するまで、日本内地を知らない「満州育ち」でいらした。『人間の條件』をむさぼり読み、「梶」が雪の荒野で息たえる最後に、うなされるほどだったわたしは、編集者として五味川さんの担当をしていた。これは縁であるし、人はなにに心を動かされるか、正直であるか否かの問題でもある。わたしは熱心な五味川番であった。
しかし、「昭和」という時代をフォローできるのか。わたしには助手となる準備はゼロというべく、古書店めぐりから、かつての新聞縮刷版のぬきがき、図書館通いと、息のつまるような9年を送ることになった。
五味川ファンであったわたしは、大岡昇平氏のとりこでもあった。お二人がスタンダールの『赤と黒』を愛読されているのを知っていたから、「対談してもらえたら」とひそかに思っていた。だが実現はしていない。大岡さんとは、『妻たちの二・二六事件』出版後にご縁がもどり、何通もの手紙がのこることになった。
「心臓はよくなりましたが、仕事疲れで暴飲暴食がたたり、目下過糖にて、順天堂に検査入院中です。ただし恢復早く順調ですので御放念下さい。ただ今後のノルマ厳しく守り、清謐人生を送りますので、スカスカ文学しか生めないかも知れません。NHKがお頼みしたはずで、よろしく。すぐ退院します。’84/6/2」
わたしがミッドウェー海戦の「運命の五分間説」は成立しないと書いて、旧海軍の軍人たちの反撃をくらったとき、誰よりも早く「公報は嘘をつく」とご自身の書かれた例証を示して擁護されたのも忘れがたい。
大岡さんは35歳で軍隊にとられたとき、東京ははじめての妻が子たちの手をひき、白っぽい着物姿で、移動する部隊に追いつく情景を書かれている。あるテレビの対談の席で途中休憩のあと、奥様をお呼びして三人になりましょう、と言うと、一瞬先生はたじろがれた。
しかし、奥様は、あれは白っぽい着物ではなく、先生が一枚だけ買った黄と黒の縞の着物で、今も箪笥の抽出しにあるとはじめて言い、銃後の日々のすさまじさへと話はひろがった。
男たちの側から戦争を書いてきた大岡さんは、さらにやるべきことがあると、その場で卒直にうめかれた。