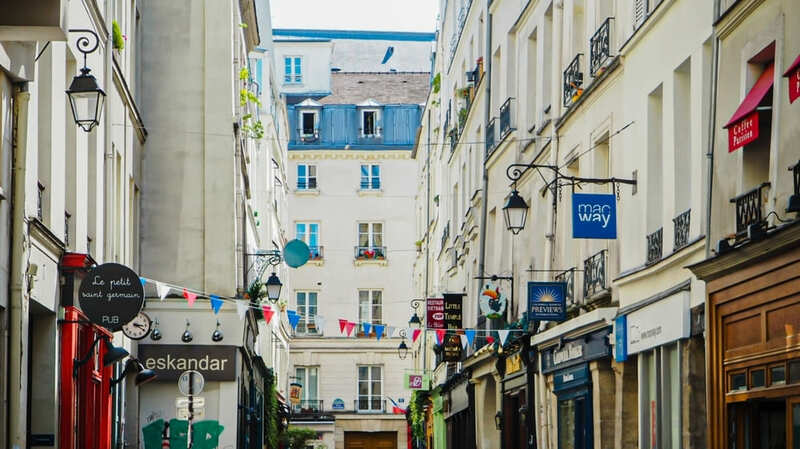2025年10月、ウィーン国立歌劇場が9年ぶりに来日公演を開催するなど、日本でも人気が高まっているオペラ。ヨーロッパ最高の娯楽・教養であるオペラとは、どのようなものなのでしょうか?今回は、歴史ライター・内藤博文さんの著書『教養が深まるオペラの世界』から一部を抜粋し、奥深い名作オペラをわかりやすく解説します。
「カルメン」と民族の時代
──普仏戦争がもたらした、フランス人によるフランス・オペラ
「カルメン」(ジョルジュ・ビゼー)
初演1875年 パリ オペラ・コミーク座
全四幕 およそ2時間45分
激情と痴情の交錯するオペラは突然変異か
フランスのジョルジュ・ビゼーの「カルメン」は、史上もっとも有名なオペラである。その人気の秘密は、観客が沸き立つ場面が詰まっているからだろう。
まずは野性と勢いのある序曲が人の心をつかみ、カルメンが歌う「ハバネラ(恋は野の鳥)」のエキゾチズム、闘牛士エスカミーリョによる「闘牛士の歌」のわかりやすいヒロイズムなどの名曲が、蠱惑的に人を魅了していく。
ただ、それ以上にオペラ全体を支配しているのは激情と痴情である。タバコ工場で働く自由奔放な女性カルメンは、真面目な伍長ドン・ホセを誘惑し、彼を密輸団の一員に引き込む。しかし、カルメンの心は移ろい、闘牛士のエスカミーリョに惹かれていく。カルメンの激情、カルメンを恋慕するドン・ホセの痴情が絡み合い、最後にホセがカルメンを殺すという惨事の中、闘牛場での歓声は盛り上がり、一つのコントラストをなす。
「カルメン」は、ある意味で突然変異のごとく生まれてきたオペラだ。「カルメン」よりも前に、これほどの卑俗な激情が噴出するオペラはなかったと記憶するし、これほどに執念深い痴情が暴発するオペラもなかった。それは突然変異にも見えるが、「カルメン」は1875年のパリに生まれるべくして生まれたオペラともいえる。「カルメン」の中にほとばしるエキゾチズムそのものが、この時代の表れだからだ。