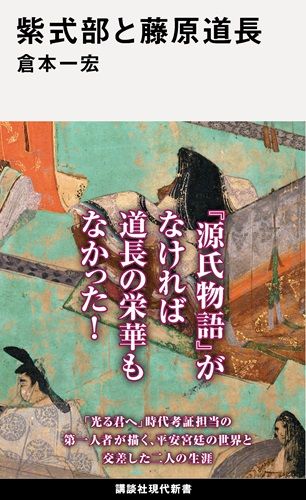大抜擢
国替えを嘆いた国盛がそのまま死んでしまった(『続本朝往生伝』)というのも、まったく根拠のない話である。
為時が本当にこの詩を作ったのならば、「いつも除目の翌朝に、無念さから天を仰ぐ」という意味で、むしろ除目の前に作ったものであろう(もしかしたら淡路守を申請した際の申文の一節だったのかもしれない)。
『源氏物語』の「少女(おとめ)」巻で、光源氏が不遇の学者を抜擢して大学が繁栄し、これが聖代の象徴とされたという記述は、紫式部とその一家にも脈々と流れる希望を、舞台を醍醐(だいご)・村上朝に設定することによって物語世界に現出させたものであろう。
なお、為時が宋客羌世昌(きょうせしょう)に拝謁した後に贈った詩というのが、『本朝麗藻(ほんちょうれいそう)』に収められている。
そこでは、「言語は異にするとはいっても、藻思(そうし。詩や文章をうまく作る才能)は同じである」と言っている。
ともあれ、為時にとっては、思いも寄らない大抜擢なのであった。
※本稿は、『紫式部と藤原道長』(講談社)の一部を再編集したものです。
『紫式部と藤原道長』(著:倉本一宏/講談社)
無官で貧しい学者の娘が、なぜ世界最高峰の文学作品を執筆できたのか?
後宮で、道長が紫式部に期待したこととは? 古記録で読み解く、平安時代のリアル
24年大河ドラマ「光る君へ」時代考証担当の第一人者が描く、平安宮廷の世界と、交差した二人の生涯!