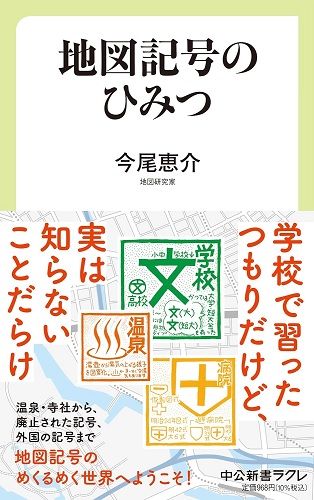「雪除部」という記号
最初の雪覆いの話に戻るが、実は「昭和35年(1960)加除」の図式までは無壁舎とは別の記号が用いられていた。明治42年(1909)図式に登場した「雪除部」という記号で、半世紀ほど使われたのである(大正6年図式では「雪除ヲ有スル部」)。
これは線路を覆う切妻屋根を上から見た様子を記号化したらしく、細長い雪覆いの屋根の端2本とまん中の棟1本、合わせて3本の細線が線路を覆って描かれ、終端部(妻部)を三角形でまとめている。
雪国の鉄道に特有の施設で、たとえば奥羽本線では急勾配の難所で知られた福島─米沢間にいくつもこの記号が描かれていた。つい先年の秋も電車が落ち葉でスリップして前進できなくなり、前の駅まで引き返したほどのいわく付きの急勾配区間である。
この峠道は今なお雪覆いが健在であるが、そこからほど近い東北本線の福島・宮城県境に位置する藤田─越河(こすごう)間にあったこの記号は戦後しばらくして消えてしまった。
地形を見ても特に雪崩が起きるとは思えない集落の脇にあり、以前から不思議に思っていたところ、古書店で見つけた昭和11年(1936)発行の鉄道旅行ガイド『旅窓に学ぶ 東日本篇』(ダイヤモンド社)にその答えがあった。
東北本線の車窓から福島盆地を俯瞰する場面の解説には、「誰も皆「右窓」に倚(よ)つて暫しそのパノラマ的風景に見惚れるうち、列車は貝田(かいだ)信号所を越へ、海抜二百米余を頂上として福島・宮城の県界の峠路を切下げた鞍部を乗り越し、やがて下り急勾配線となる。越河(こすごう)散火囲(さんかい?)延長五百八十米を過ぎ」とあった。
その散火囲というのがこれである。要するに急勾配で濛々(もうもう)と煙を吐く蒸気機関車が火の粉をまき散らすと、藁葺き屋根の集落にとって危険きわまりない。それを封じ込めるためのシェルターだから、電化されれば必要なくなるのも当然だ。
新しい地形図が刊行されてこの記号が消えたのは、東北本線が電化されたのとほぼ同じ時期であった。
※本稿は、『地図記号のひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『地図記号のひみつ』(著:今尾恵介/中央公論新社)
学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。