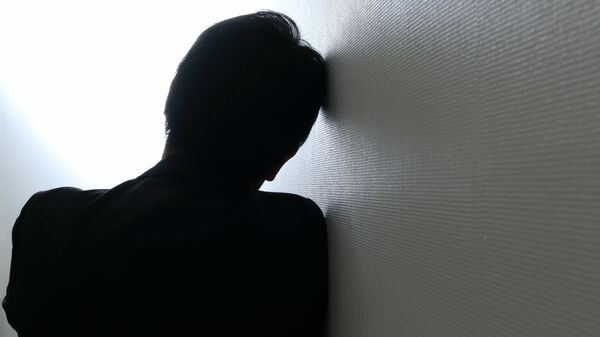インターネット上の誹謗中傷について、プラットフォーム事業者に迅速な対応を義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法」が4月1日に施行されました。脳科学者の中野信子先生は言語とはその性質上、人間の行動パターンを大きく変えてしまうことがあることを指摘し、「人間の歴史はまじないの歴史」と語ります。「言葉の隠された力」を脳科学で解き明かします。そこで今回は、中野さんの著書『咒の脳科学』から、一部引用、再編集してお届けします。
ストレスでネズミの遺伝子に影響が
慢性社会的敗北ストレス(CSDS、Chronic social defeat stress)と呼ばれる、広く用いられているうつ状態の動物モデルがある。
たとえばオスでは、自分の縄張りに別のオスが侵入するとその個体を攻撃するが、侵入した側はその攻撃から自分の身を守るために回避的な行動をとる。この状況が長く続くとき、攻撃を受け続けた側が与えられる負荷は大きくなる。これを慢性社会的敗北ストレスといい、特有の行動パターンや身体的な反応が現れることがわかっている。
一般的な人間の行動パターンを前提に考えれば、必ずしも回避することが敗北とは限らないというイメージがあろうが、これは動物を用いた研究モデルの話であるので、根拠の不明な無意識のバイアスに引きずられることなく冷静に読んでもらいたいと思う。
さて、慢性社会的敗北ストレスにさらされたネズミについて、糞便の菌叢解析や、腸管の遺伝子発現について解析を行うと、やはり腸内細菌の構成と腸管の上皮細胞において異常が見られた。メスでは、体重が減少して不安様行動を示すようになり、免疫系にも異常が生じることがわかっている。オスでは、精子に含まれる遺伝子の活性(DNAに対する化学修飾)の変化が起こり、子どもの性格にまで影響が及ぶことが明らかになった。
実際、アメリカのマウントサイナイ・アイカーン医科大学の研究チームによって行われた実験で、環境的な要因が父親の遺伝子に影響を与え、精子を経由して子どものストレス耐性に影響を与えるという報告があるのでご紹介したい。