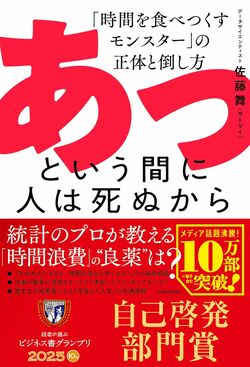親鸞聖人の「苦しみ」についての教え
<1つ目の原則:変えられないものと変えられるものを区別せよ>
今から700年程前、鎌倉時代後期に書かれた仏教書『歎異抄(たんにしょう)』は、今や世界中の哲学者や思想家を魅了する名著とされています。
作家の司馬遼太郎は、「無人島に1冊の本を持っていくとしたら『歎異抄』だ」と言っています。
また、20世紀最大の哲学者と言われ『存在と時間』を記したハイデガーは、英訳された『歎異抄』を読んで、「10年前にこんなに素晴らしい聖者が東洋にいたことを知っていたら、ギリシャ語やラテン語の勉強をせず、日本語を学んで世界中に広めることを生きがいにしただろう。しかし、遅かった」と晩年の日記に記しています。
『歎異抄』は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)の教えを、唯円(ゆいえん)という弟子が書き記したとされています。親鸞聖人は、私たちの苦しみには、「根本」と「枝葉」の2種類あるといいます。
簡単に説明すると、「枝葉」は、欲望や妄念(もうねん)、嫉妬などの「煩悩」のことで、「根本」は、死んだらどうなるか分からない、「死後が暗い心の病」と言いました。
根本の苦しみを断ち切らない限り、枝葉は、私たちを苦しめ悩ませ続けます。そして、枝葉の苦しみを、「治らない病」、根本の苦しみを、「治る病」としました。
我々は、煩悩を持ったまま、「死後が暗い心の病」を生きているうちに治すことができる、というのが親鸞聖人の教えです。