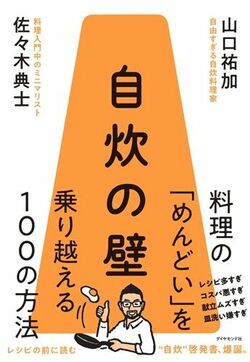時代が移り、家族も社会の形態も変わった
佐々木 ご飯にめざし、梅干しやたくあんだけ、みたいな献立は、すごく長い時代続いていたんだろうなと思います。
山口 あとは家で作った味噌と野菜でお味噌汁を作るぐらい。すぐそばに「食べられない」があったわけだから、それで充分ありがたかったと思います。
佐々木 それが素材も知識も入ってくるようになり、時間もできたから、たくさんの種類の料理を「作れてしまう」環境になった。そこからまた時代が移り、家族も社会の形態も変わったのに、料理に関しては、高度経済成長期のクオリティ、一汁三菜のような献立への期待が残っているのがしんどいということなんだと思います。
山口 現在家庭料理と呼ばれているものは、そもそも料理学校に通って習うような人たち向けの高度なもので、好きな人が趣味的に始めたものだったんですよね。でもそれが家族団らんが良しとされた時代に、「家族への愛情の証しとしてみんな作りましょう!」という強制力のあるものになった。そういう価値観が昭和の時代に作られてしまったんですね。
日本は本当に「日本人だらけのコミュニティ」で、日本人にしかわからないような高度な文脈で、すごく悩んでいるなと思います。たとえば「お弁当は冷凍食品でもいいから、何種類もおかずを入れるべき」という議論。お弁当で「2品だけ?」みたいな目線が気になるとか。別にしょうが焼きと、ミニトマトだけで充分じゃん、と思うんですけど。
佐々木 日本で花開いた豊かな家庭料理は、特別に恵まれた時代状況で成立していたということ。それが可能だった世代も、現行世代に自分たちが特別な状況下でできていたことを、押し付けてはいけないのかもしれません。そしてもう時代が変わったということは、作る人だけじゃなくて、料理を食べさせてもらう人も認識しないといけないでしょうね。