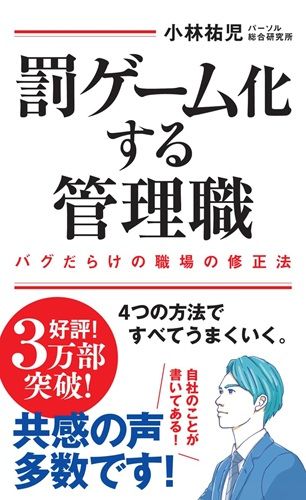メンバー層への矮小化
働き方改革のもう一つの矮小化は、改革の対象を職場全体ではなく、労働時間管理の対象である「メンバー層」としてしまった点です。その結果、残業手当の付かない管理職は、働き方改革の中で優先順位の低い位置に置かれました。そして多くの現場では、メンバー層を時間厳守で早く帰らせる分、管理職が仕事を引き取らなければならない状況が多く生まれています(第二の矮小化/メンバー層への矮小化)。
コロナ禍によって長時間労働は一時的に激減したため、コロナ禍以前の2017〜18年に行った調査のデータを見てみましょう。この時期の調査からは、管理職層のほうが、メンバー層よりも残業時間が長いことがわかっています。特に課長が最も長く、月平均31.8時間もの残業をしています。(※1)
長時間労働是正という面で働き方改革が必要なのは、圧倒的に「管理職」であるにもかかわらず、労働時間管理の外にいるため改革の対象にならず、対象は「メンバー層」に絞られる。効率化や業績目標の軟化といった変化が無いままに、会社からの「残業時間を減らすこと」というお達しに従うには、「自分が仕事を巻き取る」しかありません。部下に仕事を押し付けるような管理職は、「失格」の烙印を押されます。
働き方の効率化や労働生産性の上昇という本質を持っていたはずの働き方改革は、こうして「労働時間の上限」と「メンバー層」という二重の意味で矮小化され、そのツケは管理職の肩に重くのしかかっているのです。
(※1)パーソル総合研究所・中原淳「長時間労働に関する実態調査」
※本稿は、『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』(集英社インターナショナル)の一部を再編集したものです。
『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』(著:小林祐児/集英社インターナショナル)
高い自殺率、縮む給与差、育たぬ後任、辞めていく女性と若手──
日本の管理職の異常な「罰ゲーム化」をデータで示し、解決策を提案する。
「管理職の活性化」に悩む経営層にも、現場の管理職にも役立つ、知恵とヒントに溢れた1冊。