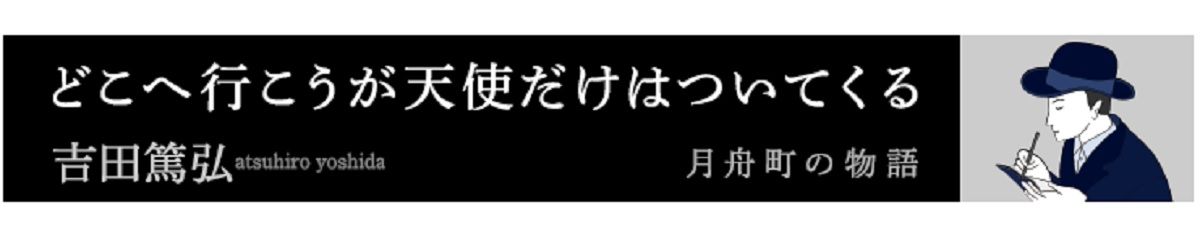手帳は兄が遺したストックで、ボールペンは同じものを探して手に入れた。どちらもめずらしいものだ。
「もしかして、お前にはこの仕事が合うかもしれんな」
兄の言うとおりになった。申し分のない仕事だと思う。
困ったことがあるとすれば、街灯調査員がどんな仕事であるか、うまく説明できないことだ。
それなりの歴史を持った職務で、電柱に灯りがともされたときから歴史は始まっている。地味な目立たない仕事なので、ほとんどその存在は知られていない。
「それでいいんだよ」と兄は言っていた。
誰にも知られることなく電柱から電柱へと渡り歩き、電灯の有無と電灯の必要、不必要を判定してゆく。
必要であるのに電灯が設置されていないときは、すみやかに設置をうながし、過剰に電灯が設置されていたり、明るさや暗さが不適切であるときは、撤去や調整をうながす。
調査は慎重に行われるが、提出書に記されるのは、電柱の番号と街灯の有無および是非を示す四つの記号だけだ。
すなわち、◎、○、△、×、の四つである。
街灯が必要と判断されたときは◎が打たれ、いまある街灯を継続して使用する場合は○、判断を保留するときは△、必要ないときは×、ということになる。

ひとつの町に足を踏み入れるとき、とりわけ、そこが知らない町であった場合、電柱の周囲を調査すれば、それで事足りるというものではない。
町にはそれぞれの性格があり、町ごとに見合った明るさの塩梅がある。
「その町の夜は街灯の明るさによって左右されるんだよ」
これも兄の言葉だ。
もちろん、町を彩るのは街灯だけではなく、駅や店や人家の灯りが占めるところも大きい。しかし、自分の経験から言うと、それでもやはり町の基調となる夜の明るさは街灯によって決められていると思う。
なぜなら、駅も店も人家も、灯りを消してしまう時間があるからだ。
街灯は、たとえそこに人がいなくても灯りをともしつづける。