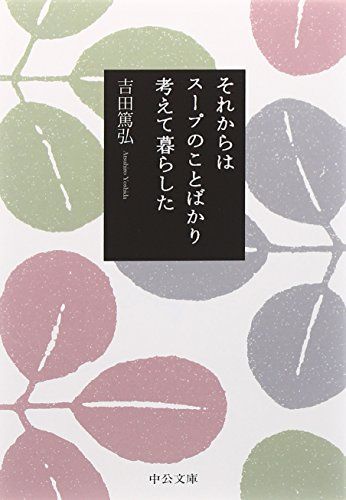(ああ)
と立ちすくみ、
(このインクを手に入れるのは容易じゃない)
と立ちこめた雲を見上げて、ため息をつく。
兄がなぜ、このボールペンを愛用していたのか分からない。見知らぬメーカーの普及品で、よく言えば、「シンプルな意匠」だが、ありのまま言ってしまえば、何の変哲もないそっけないペンだ。なのに、なぜか見かけない。
(もう、見つからないかもしれない)
うなだれる自分をなだめるように生あたたかい風が吹き、その風に乗って踏切の警報音がこちらの耳に届いた。
近くに駅があるのだろうか。
駅があるなら、周辺に店が並んでいるかもしれない。雨が降り出す前にコーヒーが飲めるところに逃げこむか、それとも、この町にはさっさと見切りをつけて、電車に乗ってしまう方がいいのか──。
インクも尽きてしまったことだし。
いきおい、足早になった。
前髪が風にあおられて額があらわになり、自分が猫になり変わった心地で知らない町の路地を進んでゆく。
甲高く響く警報音が近づいて踏切が見えてくると、光を宿した二両編成の電車がガタリゴトリとゆるやかに横切った。
路面電車のようだ。やはり、駅が近いのだろう。
速度を落としながら通り過ぎ、踏切が上がって渡ろうとすると、わずかに蛇行しながら走りゆく列車の向こうに小さな駅舎が見えた。
それだけではない。
踏切を渡った正面に年季の入った電柱が立っていて、あたりをごく控えめに照らしている。電灯はすぐ隣にある店の看板を夕闇に浮かび上がらせ、剝げかけたペンキ文字は〈南雲文具店〉と読めた。