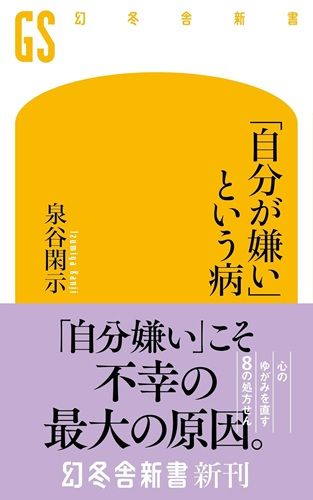自己否定はうまくいかないことを説明してくれるオールマイティカード
ひとたびそんなふうに思ってしまった子どもは、そこから先、常に自分のあら探しをするモードで生きていきます。「自分のいったい何が悪いのだろう」という解けない謎をいつか解きたいという必死の思いで、自分の欠点にばかり注目する日々を送るのです。
人はこの状態にあると、たとえ何かうまくやれたり人に褒められることがあったとしても、「そんなのは、きっとまぐれ当たりだ」「自分にできるようなことは、他の人だって当然できるはずだ」「どうせこの人は私をおだてて、からかっているに違いない」などと処理してしまい、自己否定そのものが見直されることにはつながりません。
このように一度思い込んでしまった自己否定は、自分が関わるすべてをマイナスに解釈するような認識上の引力を発生させます。そして、思春期以降になって親の未熟さや偏りにようやく気づき始めたとしても、残念ながらこの自己否定は自動的に訂正されたりはしません。
なぜなら、いわば生乾きのコンクリートのような人格形成初期にくっきりと刻印されてしまった自己否定は、もはや基本OS(コンピューターの基本ソフト)のごとく自分の認識の基礎に組み込まれてしまっていて、疑う対象にはなり得ないからです。
さらにこの自己否定というものは、うまくいかないことや不条理なこと、不愉快なことも不幸なことも、「私がダメだから」という形で見事に理由づけ、説明してくれるオールマイティカードとして機能してきているので、すでに本人の中では疑いようのない真実になっているのです。
※本稿は、『「自分が嫌い」という病』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。
『「自分が嫌い」という病』(著:泉谷閑示/幻冬舎)
「自分嫌い」こそ不幸の最大の原因――。
本書では、自分を傷つけた親への怒りを認め、心のもやもやを解消するための具体的な方法を解説。
自信を持って生きられるヒントが詰まった一冊。