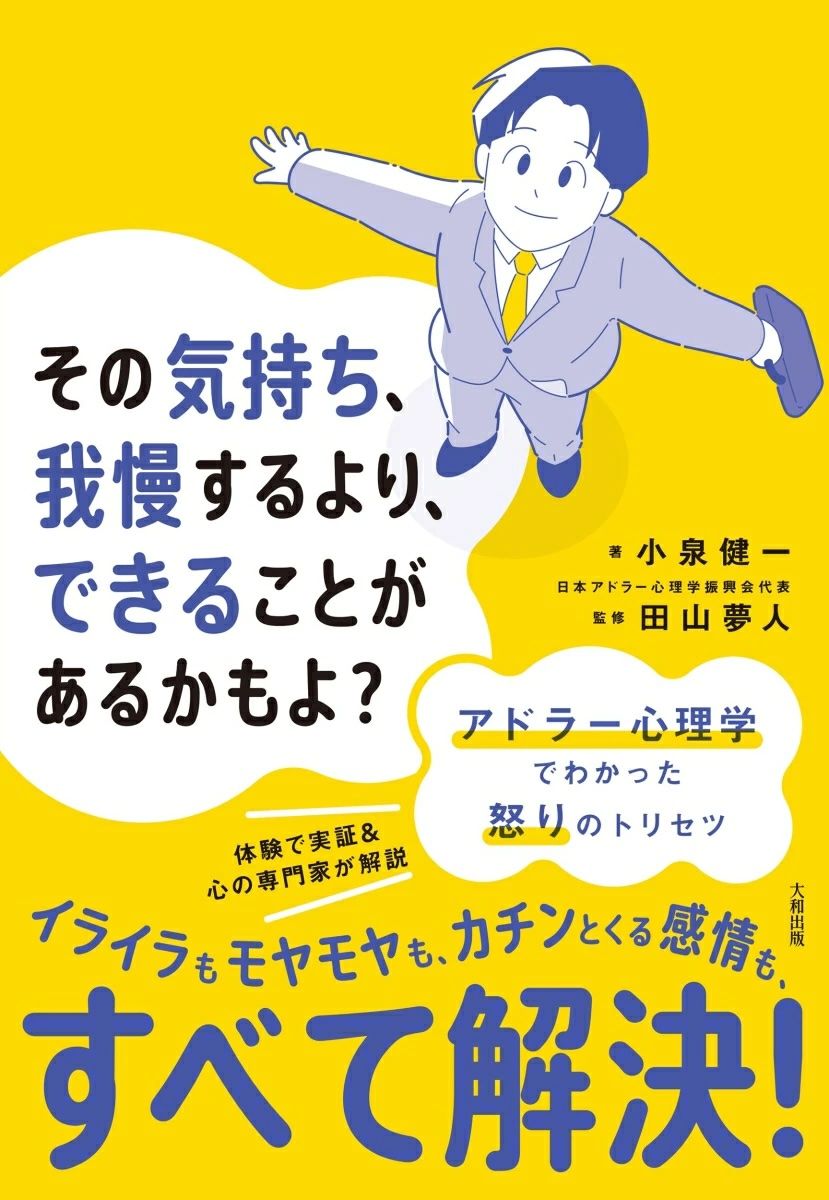5つの理論とは
1:「自己決定性」――自分の行動はすべて自分で決めているという考え方。
相手の行動にイライラしたからといって、それは相手の責任ではありません。「イライラする」という選択を取ったのは自分であり、自分に責任があります。
2:「目的論」――人の行動や感情にはすべて目的があるという考え方。
「どうして怒っているのか」よりも、「なんのために怒っているか」と考えるほうが賢明です。目的は変えることができるので、その選択した「怒り」という感情も目的次第で変えることができるからです。
3:「認知論」――人それぞれ自分の主観で物事を見て解釈しているという考え方。
同じ出来事があっても、怒る人もいればそうではない人もいる。出来事や相手の言動に対して、自分が感情を選択しているということです。
4:「全体論」――人間は分割できない統一された存在であるという考え方。
感情も行動もすべてひとつの目的に向かっているということです。「この人からの頼まれごとなんてイライラするから本当はやりたくないけど、いやいややっている」ということがあったとしても、それは「やりたいからやっている」と言えるのです。
つまり、「やったほうがいい」とどこかで思っているはずです。
5:「対人関係論」――どんな感情や行動にも相手がいるという考え方。
これは怒りだけではなく、不安や焦り、喜びなどの感情も他者という存在がいるということです。 人間は他者と関わりながら生きています。お互いに協力したり、競争したり、ときには主従関係になったりもするでしょう。
そういった中で、自分とは異なる価値観や性格の人と関われば、いろいろな感情も生まれるはずです。
自分の感情が湧き上がってきたときは、その相手は誰なのか、目的はなんなのかという視点で考えてみるといいと思います。
※本稿は『その気持ち、我慢するより、できることがあるかもよ?アドラー心理学でわかった怒りのトリセツ』(大和出版)の一部を再編集したものです。
『その気持ち、我慢するより、できることがあるかもよ?アドラー心理学でわかった怒りのトリセツ』(著:小泉健一・監修:田山夢人/大和出版)
「ああ、また怒ってしまった」と後悔ばかりしていませんか?
感情に振り回されてばかりいた「私」が実践して変わった「認知のコツ」を、専門家の監修のもとに、事例とともにご紹介します。