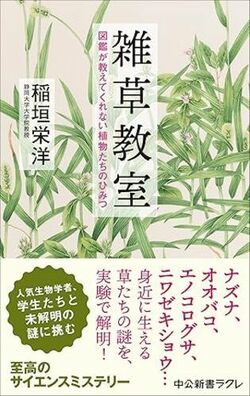アントシアニンの役割
ムラサキエノコログサの持つ赤紫色の色素は「アントシアニン」である。
アントシアニンは、植物が持つ一般的な色素である。たとえば、赤じその葉の赤い色もアントシアニンである。あるいは、秋になるとカエデの葉を赤く紅葉させるのもアントシアニンである。また、ブドウやブルーベリーの皮の色やナスやサツマイモの皮の色もアントシアニンだ。さらには、バラなどの花の色もアントシアニンによって作り出される。このように、植物は、アントシアニンをさまざまに利用しているのだ。
もっとも、アントシアニンの役割は、ただ、色づけするだけではない。アントシアニンには、他にもさまざまな役割がある。
たとえば、アントシアニンには抗菌活性があり、病原菌から身を守る効果がある。また、病原菌に攻撃されると植物の細胞は活性酸素を発生するが、その活性酸素を取り除く抗酸化作用もある。アントシアニンが私たち人間の体にも健康効果があると言われるのは、この抗酸化作用があるためである。
さらには、紫外線から細胞を守る効果や、気温が下がったときに細胞が凍るのを防ぐ役割もある。
アントシアニンはこのように多機能な物質である。そのため、植物にとっては、とても便利な万能の物質なのだ。
ムラサキエノコロは、このアントシアニンを持っている。これに対して、ふつうのエノコログサはアントシアニンを持っていない。アントシアニンがそんなに便利なのであれば、すべてのエノコログサがアントシアニンを持てば良さそうな気もする。それなのに、ふつうのエノコログサがアントシアニンを持たないのはどうしてだろう。
この理由は明確ではない。
ただ、便利な物質とは言っても、アントシアニンを生産するのにはそれなりのコストが掛かる。もし、アントシアニンが不必要な環境であれば、アントシアニンを生産しない方が有利になるのだ。
実際に、ムラサキエノコロは、河原や砂地、アスファルトのすき間のような水分が少ない場所や、気温が低い場所など、植物の成育にストレスがある場所で多く見つかる傾向がある。おそらくは、アントシアニンを持つムラサキエノコロは、そのような過酷な環境で有利なのだ。