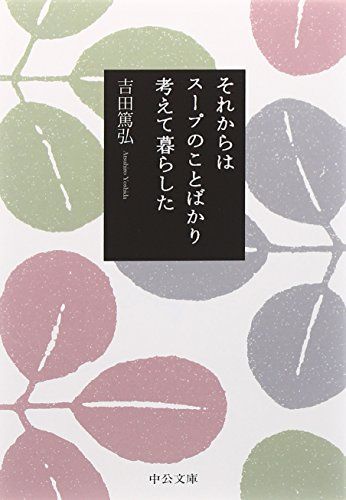母の部屋に残されたガラクタがようやく片付き、自分のアパートに戻ると、遠方から見透かしていたかのように「不器用な小包」が届いた。
正しく言い直すと、不器用な誰かが梱包した小包だ。
すぐに分かった。父からの小包だ。
父はあんなに器用にガラクタを直してしまうのに、誰かに送る小包をこしらえるのが苦手だった。
正しく言い直すと、父は誰かのために何かをするのが苦手なのだ。
誰かではなく、いつだって自分を喜ばせるために手を動かしている。
それは一見、自分勝手に見えるだろうが、決して他人の手を煩わせないという意味では一貫していた。
父はねじ曲げられなかったのだ。抗って生きることを選ばなかった。父なりに挑戦はしてみたが、結局、「ひとり」を選んだ。そういうことだ。
ぐるぐる巻きのガムテープを呪いながら剝がし、でたらめに丸めて突っこまれた新聞紙に悪態をつきながら取り除き、最後に思わせぶりな白い布に巻かれたものを父の手つきをなぞるように解いたら、
「えっ」
と思わず声が出てしまうようなものが中からあらわれた。
ちょうどいい大きさの置き時計だ。
「あっ」
と声がひるがえる。
あのとき直していた飛行時計だ。円いガラスの奥に並んだ数字と針の意匠に魅かれたのを思い出す。
両手で包みこむように持つと、その律動が伝わってきた。
小さな生きもののように。「前へ前へ」と歌うように。
直してみないことには分からない、と父は言っていたけれど、わたしの手の中で、それはいま、たしかに動いていた。