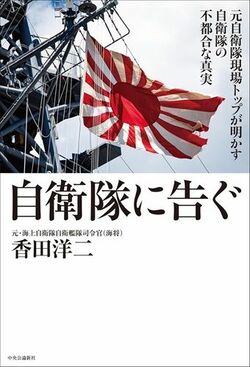効果が減じていった航空特攻作戦
問題は、何もミッドウェー海戦だけではない。旧海軍の失敗は他にもある。沖縄戦における航空特攻作戦、いわゆる神風特攻隊は、その最たるものだった。
航空特攻作戦は、二度と繰り返してはならない外道な作戦だ。ただし、フィリピン沖で始まった航空特攻作戦は、それなりの軍事的合理性があった。敵に損害を与え、友軍の海上作戦、地上作戦を支援する役割を果たしたという評価はある。
このままいけば100対0で負けるかもしれないが、90対10まで持っていけば、戦況をなんとか持ち直せるのではないか、そこに賭ける、ということだ。特に、長い飛行甲板を持つ敵の空母を使用不能にするという意味では、決して無駄死にではなかった。10機のうち9機が撃ち落とされても1機残ったゼロ戦がなんとか一撃を加えるという作戦は、それ自体は人道にもとる作戦だが、戦中にはある種の「合理性」はあったのだ。
だが、そのうち攻撃目標は空母よりはるかに戦術的価値の低い戦艦や小型艦にも広げられていき、米海軍もカミカゼへの対処方法を徐々に改良させていった結果、航空特攻作戦の効果は減じていく。
そして、米軍が沖縄に上陸した時点で、航空特攻攻撃を続ければ旧海軍は兵力を出し切って干上がってしまうことは目に見えていた。旧海軍が沖縄周辺で行った航空特攻作戦は、軍事作戦と呼べるような代物ではなかった。ほとんどの特攻機は敵艦に突っ込む前に撃ち落とされ、作戦効率は極めて低いものになっていた。
沖縄戦の地上戦闘の帰趨が決してしまい、1945年6月23日に組織的戦闘は終了するのだが、その後も、本土決戦に備えつつも散発的に、相当数の神風特攻隊が出撃している。