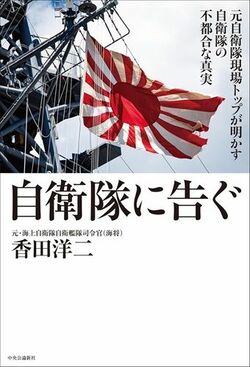ハンモックナンバーを基にした人事管理制度
ちなみに、海軍兵学校の卒業席次は「ハンモックナンバー」と呼ばれる。海軍兵学校では在校時から成績順に席次が決められ、寝室のベッド(ハンモック)まで成績順であった。首席だった生徒が2位、3位へと落ちれば、それに伴いベッドの位置も変わったといわれている。
このハンモックナンバーは卒業後に固定されるわけではない。例えば、首席の人間が何か不祥事をしでかしたら、ハンモックナンバーの順位は落ちる。些細なトラブルもこの順位に影響を与える。順位には変動があるとはいえ、一般の人が同窓会などで「中学校ではお前はトップだったなあ」などと思い出として語る類の話ではなく、いつまでたってもリアルタイムで重要性を持つのがハンモックナンバーなのだ。
卒業席次が極端に低い人間がトップに上り詰めることはまずないし、トップの人間が最下位に沈むということもほとんどない。つまり、海軍軍人としての実務だけで評価するのではなく、いつまでたっても学校の成績が付いて回る慣習なのだ。
脱線するが、例外が米内光政海軍大将である。卒業席次は125人中68番であった。海軍大臣として山本五十六海軍次官らと共に日独伊三国同盟と対米戦争に強く反対し、終戦時には総理大臣である鈴木貫太郎海軍大将のポツダム宣言受諾案を強く支持して我が国の混乱なき終戦の実現を支えた、昭和天皇の信頼も最も厚い旧軍人の一人であった。
話をもとに戻す。こうしたハンモックナンバーを基にした人事管理制度は、海上自衛隊にも引き継がれている。私は人事関係の部署に勤務した経験がないので、以下は私の体験に基づく推察となることを、まずお断りする。
旧海軍ほどではないが、海上自衛隊では、防衛大学校の入校成績や卒業成績、幹部候補生学校での卒業席次がかなり重い人事評価の項目となっていた。初級幹部として部隊に勤務した後に、筆記試験と論文選抜により優秀な者が指揮幕僚課程という幹部養成コースに選抜される。旧陸海軍では「陸軍大学」「海軍大学」と呼ばれていた課程だ。この指揮幕僚課程学生選抜は、筆記試験と論文及び口頭試問からなる。
つまり、部隊実務の優劣よりもペーパー試験や論文に長じたものが成績の上位に立つ傾向にある。もちろん、それで終わりではなく、選抜後1年間の幹部学校学生修了時の成績が、新たなハンモックナンバーに影響することとなる。
本来であれば、海軍軍人は学校の成績ではなく、艦という現場での実務能力や、戦闘のような究極の事態において腹が据わっているかどうかという人間性を見なければならないはずだ。残念ながら、旧海軍は最後まで、試験の成績や通常の業務処理能力に優れる人物を重んじすぎたことは否めない。
先の大戦は、最後は国力の差で負けるべくして負けたことは確かだが、人的施策として旧海軍には大いに反省するところがあるのではないか。それにもかかわらず、海上自衛隊は旧海軍の妥当とは思えない人事制度の多くを踏襲してしまっているように思える。