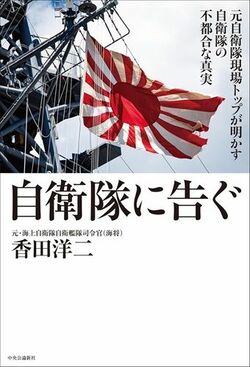陸上自衛隊は米海兵隊から見れば不安定な戦闘組織
本来であれば、軍隊はピラミッド型の組織であるべきで、下から陸士、陸曹、陸尉、陸佐、陸将というように構成されるとすると、一番下の陸士が一番多くなるのが自然である。
陸士、つまり若手で心身ともに強健な「兵」の役割は、近接戦闘において特に重要となる。近接戦闘とは、宇宙やサイバーのような新たな領域や、ドローンに代表される新兵器が使用される今日の戦場でも、戦闘の勝敗を決する最終段階で多く見られる戦闘の形態のことである。歩兵部隊が最新かつ強力な個人携行火器などの装備を使って近い距離で対峙する敵部隊と戦い、撃滅することを目的とする地上戦闘だ。
ところが、陸上自衛隊は陸士が圧倒的に少なく、米海兵隊から見れば不安定な戦闘組織ということになってしまうのだ。米海兵隊と共同作戦を行うにもうまくいかないのではないか、というのが論文執筆者の議論だった。
論文ではさらに、陸上自衛隊上級幹部(将校)が多いことも問題視していた。それはそうであろう。海兵隊の場合は大佐の連隊長が2000人を動かすのに対し、陸上自衛隊は大佐に当たる1等陸佐の連隊長が600人を動かすとなれば、陸上自衛隊が2000人を動かすためには3人以上の上級将校が必要となる。
それだけ指揮する人間が多ければ、無駄な時間とスタッフが増えてしまうことになりかねない。一つの行動をとるために判断を下す必要がある部署のことを自衛隊では「結節」と言うが、結節が多ければ多いほど判断は遅くなる。
米海兵隊は一分一秒を争う上陸作戦を担う。ゆえに海兵隊が目指すべきこと、海兵隊の特性として、「agility」(敏捷性)という標語を好んで使っている。陸上自衛隊は命令が出るのが遅いし、その命令自体も、結節ごとに理解を確認しながら進めるので、全体としての敏捷性に欠ける、というのが海兵隊中佐の論文の主旨だった。
海兵隊中佐の論文自体は、南西諸島の地理的条件や日本国憲法の理解に問題があったので私は「掲載不可」とせざるを得なかったが、米海兵隊の本音がよく分かる論文だった。このほかにも、師団の規模が日米の間であまりにも違い過ぎるため、共同作戦に支障をきたす恐れがあると論じた論文もあった。