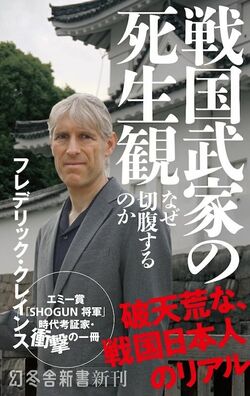政治の舞台でも女性が活躍していた
また、政治の舞台でも女性が活躍しており、家督は原則として男性が相続することにはなっていたものの、後継者候補が幼少であったり、ふさわしい男子が不在であったりすれば、女性が当主や城主を務めていました。
よく知られるように、今川氏親の妻であった寿桂尼(じゅけいに)は、夫の病気中および死後に長年にわたって今川家の政務を執り行い、女戦国大名として領国支配をこなしました。
また、秀吉の側室であった淀殿は、夫の死後に秀頼の生母として豊臣家の前面に立って政務にかかわりました。
さらに、豊後の立花道雪(戸次鑑連)の娘ぎん千代は立花城の城督・城領・諸道具を譲られたとされています。
ただ、このような女城主の存在は例外的であり、どちらかというと、武将たちのそば近くで支える役割の方が一般的でした。
たとえば、家康が最も信頼する側室の一人であった阿茶局は、諸大名に対する家康の取次役や使者役も担っていました。
さらに、慶長19(1614)年の大坂冬の陣では、女性たちが講和交渉を担っていました。
徳川方の代表は阿茶局で、豊臣方も淀殿の妹の常高院(京極高次夫人)が交渉を託され、両者が講和をまとめています。
大坂の陣の表向きの原因とされる方広寺鐘銘事件の際も、豊臣家は大野治長の母の大蔵卿局を家康のもとに派遣して、弁明させていました。
武家の女性たちが重要な役割を担っていたことは、秀吉から正妻寧々への書状や家康から娘亀姫への書状からも読み取れます。
戦国時代の女性の文通は断片的にしか残っていませんが、それらの書状から垣間見えるのは、江戸時代と比較すると、女性が政治により深くかかわり、より対等な扱いを受けていたことです。