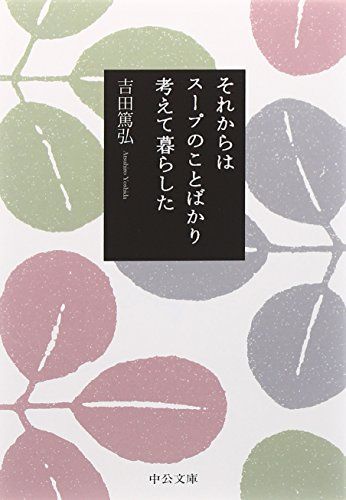理想的な証明写真が撮れるまで、カカは何度もブースに通っていた。
といって、うまく撮れたところで、その写真を何かに利用するわけではない。特にあてはなかった。
ただ、「証明写真」という言葉に強く魅かれていたのだ。自分がいまここにいることの証明と、ここにいたことの証明。
スマホの自撮りでは意味がなく、この町に据えられたブースで、この町に据えられたカメラに撮ってもらいたかった。自分で撮るのではなく、町に撮ってもらったような気がするから。まさに、「この町にいたことの証明」とでも言えばいいのか──。
しかし、三日つづいた見張りの三日目にカカは自分が嫌になった。
これはもう、ストーカーと呼ばれてもおかしくない。仮に自分の予測が的中し、彼女がふたたび証明写真を撮りに来たとしても、はたして、自分は「あの」と声をかけられるのか。もし、「あの」と言えたとしても、そのあと、どうつづければよいのか。
「じつは、あのコーヒーショップの、あの席からずっと見ていたんです」
などと言ってしまったら、間違いなく引かれる。
カカは時間稼ぎにちびちびと飲んでいたコーヒーの残りを一気に飲み干し、勢いよく立ち上がって、極彩色の鳥みたいに体を震わせた。イヤリングとネックレスとブレスレットと三つの指輪、それらが一斉にチープな色を震わせてチープな音をたてた。
(わたしはいつだって運命を信じてきたんだけど──)
そう、うまくはいかないこともある。
それに、運命というのは自分でどうにかできるものではない。いくら作戦を立てて、自分が望むところの運命を引き寄せようとしても、運命の女神がその気になってくれなければ、こちらに微笑んではくれない。
カカは店を出ると、斜め向かいのブースを一瞥し、名残惜しそうに背を向けかけたが、
(そうだ、いまのこの気持ちを写真にのこしておこう)
そう思いついて、いつもどおりブースに身を忍ばせた。