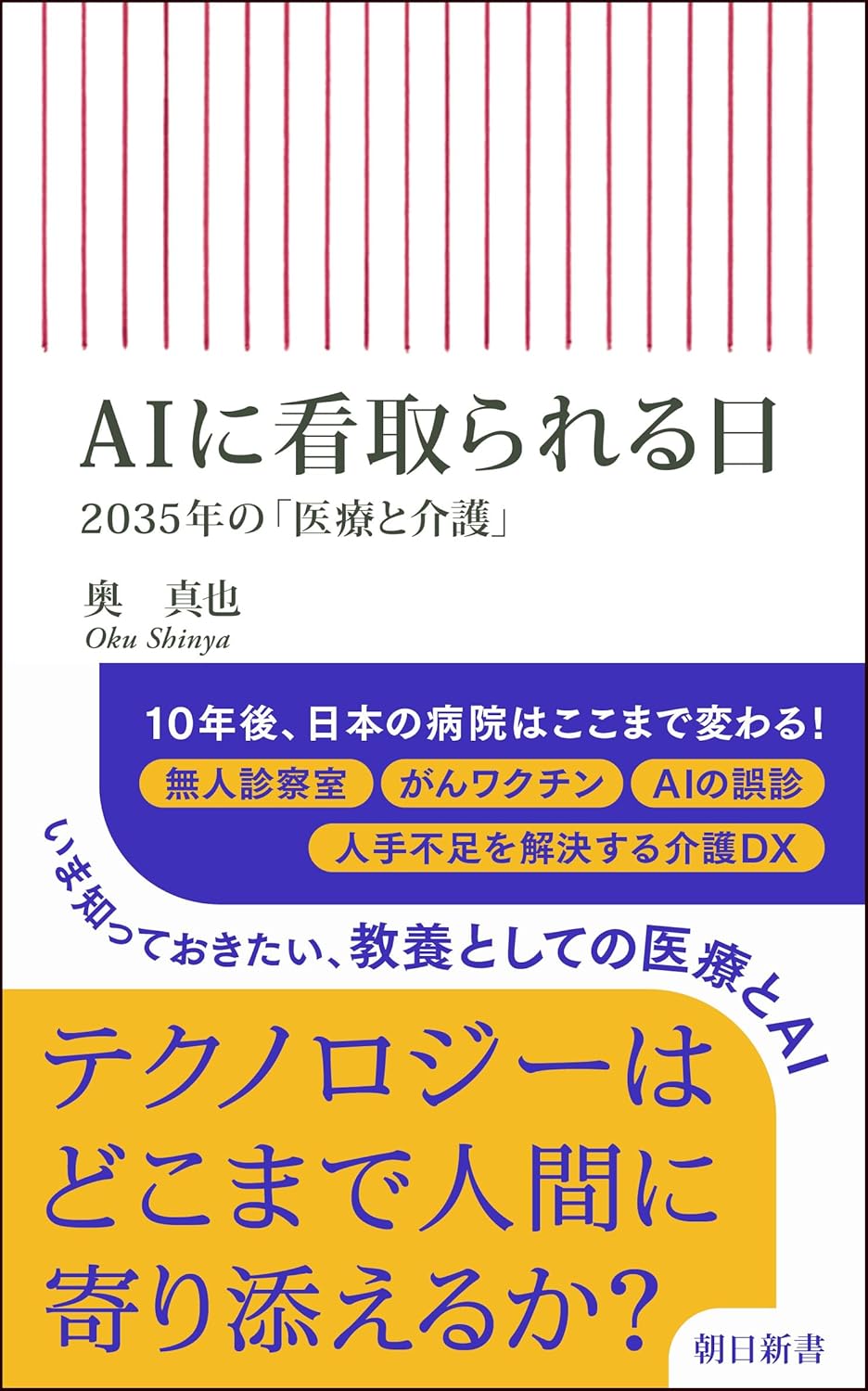AIが変える診察室の風景
現代の医療では、AIの登場以前から「知識の外部化」は始まっていました。かつて名医だけが持っていた職人芸のような暗黙知は、診療ガイドラインという形で外に記録され、医師の判断のばらつきを減らす役割を担っています。
1990年代以降、エビデンスに基づく医療が進み、関連学会が最新の研究成果をもとに治療の手引きを示すようになりました。ガイドラインはいまやウェブで即座に参照でき、診察中に医師がパソコンで確認することさえ珍しくありません。
頭に入っていなければ、診察中に医師がパソコンでさりげなく確認することもあります。薬の名前や用量も、銀行振込の際に支店名を入力するように、数文字で検索すればすぐに必要な情報が出てくるので、だんだん記憶に頼らなくなってきています。風邪や高血圧といった「よくある病気」では、誰が診ても同じ診断と治療にたどりつける時代ともいえます。
診察室の医師と患者さんとの会話やその記録は、AIによって大きく変わりつつあります。日本の診療現場でもkanaVoやWarokuなど、診察室の会話をリアルタイムでテキスト化し、要約して電子カルテに自動入力するAIシステムが導入され始めています。
実際に、これらのAIによって医師の記録業務は大幅に軽減され、患者さんとの対話に集中できる環境が整いつつあります。アメリカやカナダでもTaliやHeidiなどの診療内容記載AIが導入され、医師の作業時間を半減以下に抑えた事例が報告されています。
介護領域でも記録の自動化は進んでいます。例としてCareViewerが、北欧の健康予測AIと連携した介護記録、健康状態可視化機能を備え、2024年10月から実証実験を開始しています。
放射線科や皮膚科の画像診断だけでなく、従来は内科や外来診療などの「対話が中心だからAIには無理」と信じられていた診察領域でも、いやそこだからこそ、AIが日常業務に深く入り込む時代が到来しています。
※本稿は、『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(朝日新聞出版)の一部を再編集したものです。
『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(著:奥真也/朝日新聞出版)
10年後、日本の病院はここまで変わる! 無人診察室、がんワクチン、AIの誤診、人手不足を解決する介護DX……。
未来の医療が描く、これからの生き方、死に方とは? 直面する変化と課題、打開策を最新研究から論じる。