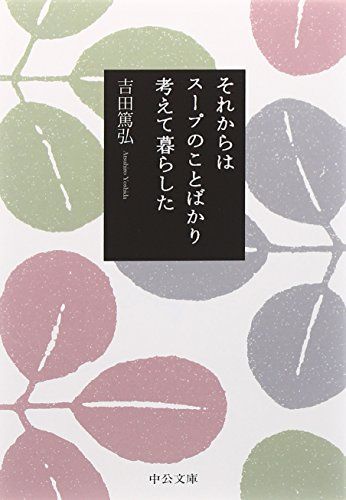その名もない食堂の夕食がどれほど忘れがたいものであったか、自分はそれを言い表す言葉を持ち合わせていません。
食堂の中には白い猫と黒い猫が居座っていて、照明はおさえられ、店の給仕をつとめる女性にタモツさんが声をかけたり、何人かの客が、「おお、タモツ」「今晩は、タモツ」と挨拶してくる様子が、「夜の食堂」と題された一枚の絵のようでした。
自分もまたその絵の中におさまっている一人なのだと思うと、その夜に起きたことは、絵の中のまたとない青い夢でした。
音楽が流れていない食堂は暖簾が風を撥ね返してくれるおかげで静寂に包まれ、客たちが操る食器の音と、彼らがひそやかに交わしている言葉が青い夢にアクセントを与えています。
「またかい?」
と誰かが声をひそめて言いました。
「よそ者の仕業だよ」「よそ者って?」「最近、他の町からやってきた若者が幅をきかしてるだろ? いや、ちょっと目を離していた隙にね」「やられたのか?」「袋ごとなくなってた」「そいつはいただけないね。よそ者って、たとえば、どんなヤツだ?」
食後のコーヒーを飲んでいました。タモツさんが注文してくれたのです。
青い夢の中に自分とタモツさんのコーヒーカップが差し向かいに置かれ、その香りの向こうで、
「どんなヤツだ?」
と、いまいちど囁かれました。
視線を感じました。
隣のテーブルの三人連れが、かわるがわる自分を見ています。
タモツさんが飲みかけのコーヒーカップをテーブルに戻し、その音が食堂全体に響きわたると、
「テツはそんなヤツじゃない」
タモツさんはそう言いました。
「オレは分かってる」
と立ち上がり、
「テツはそんなヤツじゃない」
誰に向けてでもなく、食堂に向かってそう言っているようでした。