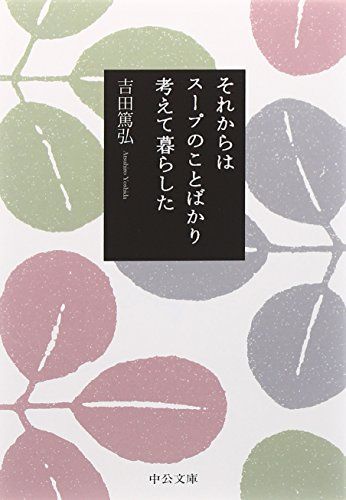「ちなみに、お父さんはどんなお仕事をされているの?」
「サンドイッチ屋です」
「え? サンドイッチ? 本当に?」
「桜川の〈トロワ〉っていう店です。この食堂もいいですけど、うちも結構いいんですよ」
そうか。そういうことか。
小説家を目指してはいるけれど、もしかして、自分はお父さんの店を引き継ぐかもしれないと心の隅でそう思っているのだ。「小説家になりたいとは限りません」というセリフは、そんな葛藤のあらわれだろう。
わたしもそうだったから、よく分かる。
文房具屋は子供の頃から好きだったけれど、自分の未来が決められてしまうのは、どうも面白くない。
「もし、よかったら、一度、うちのサンドイッチを食べてください」
「ぜひ。ちょうどいま、おいしいサンドイッチを探しているんで」
「そうなんですか」
「こっそり食べれるやつ。誰にも気づかれないように──」
それで行ってみたのだ。
隣町まで。サンドイッチを買いに。
✻
可愛らしい店だった。入口のガラス戸に数字の「3」が大きく白で描かれ、その下にトロワとあって、「サンドイッチの店 朝から夕方まで」と小さく配されていた。
ドアを押して中に入ると、カウンターがひとつあるだけで他には何もない。カウンターの中に、リツ君のお父さんにしてはずいぶんと若いけれど、「青年」と呼ばれる時期はそろそろ終わりと思われる彼が、「いらっしゃいませ」と声を響かせた。
どういうわけか、どこにもサンドイッチが見当たらず、カウンターの上にメニューらしきものが立てかけてある。
ハムのサンドイッチ、きゅうりのサンドイッチ、チーズのサンドイッチ、たまごのサンドイッチ、いちごジャムのサンドイッチ、あんずジャムのサンドイッチ、じゃがいものサラダのサンドイッチ──オムレツのサンドイッチなんていうのもある。サイドメニューでスープもあった。
「ご注文をいただきましたら、すぐにおつくりいたします」
と彼がそう言うので、
「あの──」
とわがままなお願いをしてみることにした。
「おかしなことを言うようですけど、なるべく小さくつくっていただけますでしょうか」
「小さく?」
「はい。こっそり食べたいんです。誰にも気づかれないように」
「なるほど」
と彼は大きく頷き、
「分かりますよ。じつは、僕もそうしているんで。映画館で、こっそり食べるときに」
そう言って、彼はもういちど大きく頷いた。