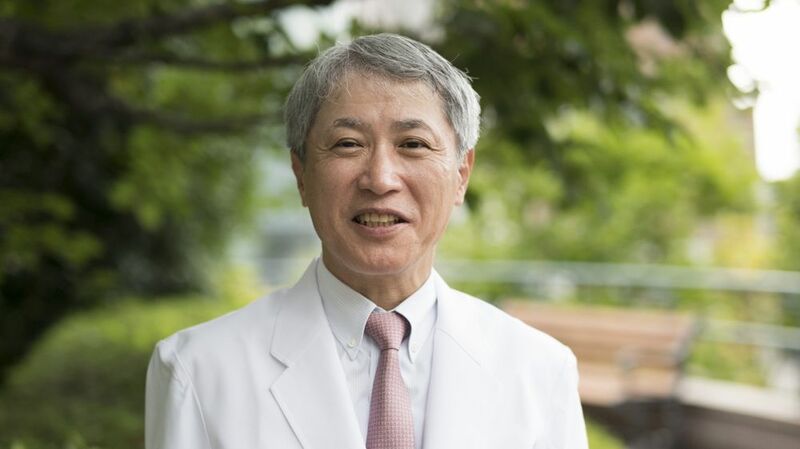厚生労働省の「令和6年 人口動態統計」によると、日本人の死因第2位は「心疾患」で、22万6388人が亡くなったそうです。そのようななか、「血管や心臓の病気は、長年の生活習慣が大きくかかわっています。そして、加齢とともに発症する頻度は格段に高まります」と話すのは、2012年に当時の天皇陛下(現・上皇陛下)の執刀医を務めた、心臓血管外科医の天野篤先生です。今回は、天野先生の著書『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』から一部を抜粋し、血管と心臓の守り方をご紹介します。
血尿、頻尿、乏尿……いずれも心臓の状態に関係している
尿検査は病気を発見する入口
健康診断や人間ドック、医療機関での診察で、ほとんどの人は「尿検査」を受けた経験があるのではないでしょうか。尿検査は体への負担が少なく、いちばん手軽な検査といえるかもしれませんが、「病気を発見する入口」として、じつにさまざまな事柄がわかります。
量、比重、色、成分などを調べることで、主に次のことを把握できるのです。
●尿タンパク=尿に排出されたタンパク質の量。
●尿糖=尿に排出された糖分の量。
●尿潜血=尿に血液が混ざっていないか。
●尿沈渣(にょうちんさ)=尿の沈殿物に、どのような物質が排出されているか。
尿検査の結果から、どんな病気が隠れているのか、いわゆる内科的な病気のうち、呼吸器疾患、消化器疾患を除けば7~8割は推測できるのではないかと考えられます。
尿は腎臓でつくられます。腎臓は全身の血液中で産生される老廃物や塩分をろ過し、尿として体外に排出しているのです。腎臓は多くの病気と深いかかわりがあり、尿はその腎臓がトラブルなくしっかり働いているかどうかのバロメーターになるのです。