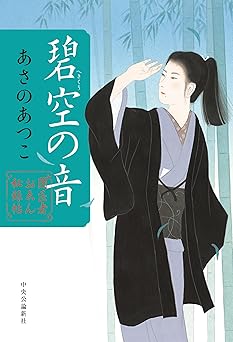頬に刀傷があっても、眼光が鋭くても、仁王のような顔立ちであっても、怖い。まして、力のない女、子どもからすれば震え上がるほどの怯えを感じるだろう。けれど、一番恐ろしいのは人の記憶に残らない顔だと、おゑんは思う。
誰にでもなれて、容易く人の群れに紛れる。
ここにいたのか、いなかったのか、わからなくなる。そういう者こそ怖いし、厄介だ。滅多に出会いはしないけれど。
「それが、十日ほど前になると思います。おつるちゃんから話を聞いて、あたし妙に気にはなってたんです。でも、それだけで先生を呼ぶのも気が引けて……先生がとても忙しいのあたしも知っているから、このまま何事もなければ忘れようって思ってました。でも、ついこの前ですけど、番頭新造の一人があたしに同じことを問うてきたんです。今度、おゑん先生はいつお出でなのかとか、どちらにお住まいなのかとか」
眉を顰める。嫌な気配がじわりと胸に染みてきた。ただ、話の先は読めない。
「あたし、なぜ、そんなことを問うのだと逆に問い詰めました。すると、しどろもどろになって、そのうちに俯いてしまって。それでも、さらに問い詰めたら白状したんです。先生の住処(すみか)や吉原に来る日を調べてくれと頼まれたって」
「へのへのもへじにかい?」
お小夜は僅かに首を傾げた。
「おつるちゃんの出会った男とは違うような気がします、番頭新造に言わせれば、なかなかの伊達者(だてもの)であったようで、役者顔のいい男だったそうです。そういう男に頼まれて、金まで握らされて、その気になってしまったとか。あれは、作り話じゃないと思います」
番頭新造に作り話をする要はないだろう。とすれば、少なくとも、へのへのもへじと役者顔の二人がおゑんのことを探っていることになる。
この吉原で。
どうにも、わからない。おゑんには思い当たる節が一つもなかった。
「どうも、ピンとこないねえ」
独り言のつもりだったが、お小夜は少し驚いたように片眉を上げた。
「えっ、そうなんですか」
「そうですよ。あたしは一介の医者です。住処だって、ここに診察に来る日だって隠しているわけじゃない。そんなもの公にしたって意味がないから、言わないだけですよ。密か事でも何でもない。知りたけりゃ容易く、知れますよ。でしょ? なのに、なぜ陰に隠れて、こそこそ探ったりしているのか。さっぱり掴めないねえ」
「先生、心当たりはないのですか」
「全くありませんね。だいたい、あたしを探って誰が得をするのか。何を得られるのか。どう考えたって何にもないじゃありませんか。ええ、ほんとに欠片(かけら)も思い浮かばないよ」
「先生に懸想したんじゃない」
つるじが身を乗り出した。お小夜とおゑんに同時に見詰められ、頬を赤らめる。
「だって、それなら話の筋が通るでしょ。先生に一目ぼれした誰かが先生のことを知りたくて、探ってるの。堂々と尋ねられないから、裏でこそこそやってるの。あたしも、時々、花魁への文を頼まれたりするもの。客になるだけの金はないけれど、心の内だけは伝えたい。誰にもわからないように、渡してくれないかって。そういうの受け取ると旦那さまに叱られるから、お断りするけれど」
「ちょっと、ちょっと止(や)めておくれよ」
おゑんは思わず苦笑してしまった。
「当代随一の花魁と比べられるなんて、あたしには、えらく分が悪いじゃないか」
「……でも、確かに筋は通りますよね」
お小夜が呟く。眉間に深く、皺が寄った。
「お小夜さんまで何を言ってるんだか。団子の串じゃあるまいし、通ればなんでもいいって話じゃないだろうに」
「あはっ、団子の串だって」
つるじがけらけらと笑う。少女の朗らかな笑声だ。
「笑い事じゃないよ。じゃなにかい。へのへのもへじと役者顔と、男二人が同時にあたしを見初めて、探り始めたってことかい。あり得ないだろう」
「なくもないと思いますけど……でも、先生」
お小夜の眸に影が走った。不安? 困惑? 心配? 何の影だろうか。
「もう一つ、気になることがあって。実は、それで、あたし、先生に文を書こうって決めたのです。もちろん、文を出せば先生が来てくれるかもって下心はありましたけど」
お小夜の頬も薄紅色に染まった。薄紅色の頬のまま話を続ける。
「番頭新造を白状させた翌日……中引けの拍子木が鳴ったころだから翌々日になるかしら、ともかく、真夜中に羅生門河岸でちょっとした諍い事があったみたいなのです」
中引けは九つ時。今日と明日が入れ替わろうとする刻となる。妓楼は賑わいの盛りを過ぎ、大引けに向けて、緩やかに静まっていく。そんな頃合いだ。
「詳しくはわからないのですが、客同士の諍いだったらしく男が一人刺されて血だらけで転がっていたとか」
「その男、亡くなったのかい」
「おそらく、死んだのではと思われます。あたしが聞いた限りでは、相当に血を流していたそうですから。そして、刺した方がどうなったのか、捕まったのか逃げおおせたのか、そちらもわかりません。ここは、吉原ですから」
「そうだね」
頷く。吉原では何もかもが曖昧になる。人の生き死にでさえ生々しく扱われることはない。いつの間にか人は消え、新たな者が流れ込む。
ちょっとした刃傷沙汰が二つ、三つあって、男が……。
甲三郎の言葉を思い出す。
あれだろうか。甲三郎が変事にも入れなかったごたごたに、お小夜の心は引っ掛かった。
「これも、噂だけでちゃんと確かめてはいないのですが、その殺された男、役者紛いの色男だったと小耳に挟んだのです」
「えっ」と、つるじが肩を窄めた。今度は驚きで頬に血が上る。
「お小夜さん、じゃあ、番頭新造にあたしのことを尋ねた男と羅生門河岸で殺された男、これが重なると考えておいでかい」
「わかりません。わからないことがほとんどで。こんなあやふやなまま、先生をお呼びしてごめんなさい。でも、あたし、怖かったんです。どうしてだか、とても、とても怖くてたまらなくなって……だって、剣呑じゃないですか。二人の男が先生を探っていて、そのうちの一人かもしれない男が殺された。どう考えても、剣呑で不穏じゃないですか。あたし、じっとしていられなかったんです。だから……」
おゑんはお小夜の膝に手を置いた。
「ありがとうよ、お小夜さん。報せてもらえて、よかった。知っていると知らないとじゃ大違いさ。けど、あとはあたしが引き受けるよ。自分のことだからね」
「引き受けるって……どうするんです」
「まずはお返しさ。男たちのことを探り返してみる。相手の正体がわからぬ限り、動きようがないからね」
お小夜の頬からすっと血の色が引いた。
(この章、続く)