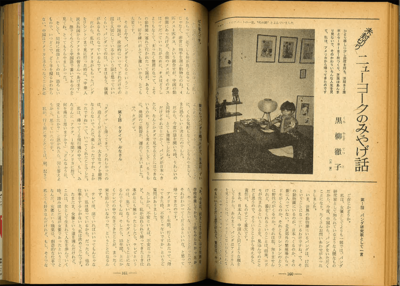テレビは、出ていればいいってもんじゃない
「タダイマ」と帰ってきて、うれしかったのは、迎えてくださる方が、大きなモノを期待なさらないで、ただ「楽しかったですか、よかったですね」って、いってくれたことでした。
私は、帰ってくる飛行機の中で、もし、みなさんに「アナタ、1年間アメリカに居て、何を得たと思いますか?」「どんなふうに、変りましたか?」と訊かれたら、何と答えようかと、思っていたのです。
私が、行く前に考えたことは、朝、起きて「あ、今日は、何をしようかな」って生活を学校卒業してから、1回もやらなかったから、やってみたいな、ということだったのでそれがわかってくださるといいな、と思って帰ってきたのです。
アメリカへ、1年間、行くにあたって「帰ってきた時、不安じゃないですか」というご質問がありました。
たしかに、不安といえば、不安だったけれど、もし、私が忘れられて帰ってきたとき仕事がなにも無かったとしたら、テレビというのは、出ていなくちゃダメ、ということになるんですもんね。そしたら、15年間、とにかくテレビの中で生きてきたことが、まったく実を結んでいなかった、ということになるんです。
テレビは、出ていればいいってもんじゃないと、私も思っているから、だったら、他の仕事をするしかないと、私は決めてたんです。
たまたま、女優という道を選んだけれど、これは、女として生まれて人生を歩んでいく時、踏み出した道が女優であったということなんだ。女優という職業は、創造的な仕事で私とても好きなんだけれど、もし、そうでなくなっても、今と同じように、自分らしく生きていこう。不安がっていても、仕方がない、と、出発したのでした。
「タダイマ」といったら、みなさん忘れないで、お帰りなさいと、声をかけてくださった。レストランの人、道で逢う人、タクシーの運転手さん、文房具屋さん、八百屋さん、そして俳優のお友だちも。
岡田真澄さんは、雑誌の対談の相手に招んでくださってね。終ったら小さい声で自分がフランスから帰ってきた時、貯金も全部つかいはたして、全然お金が無くて困ったから、対談料なんか貰うとうれしいと思ってさ、といってくれました。
「いいじゃない。行ってらっしゃい。行くんなら、今のうちよ」と、とても呑気に送ってくれた母は「どうだった。よかったじゃない。また、行きたくなったら行けばいいわ」といってくれました。
いちばん私が逢いたかった2人の姪と1人の甥は、ちょっと見ないうちに、ずいぶん大きくなっていました。その小さい子どもたちの、4歳から5歳、2歳から3歳、半年から1年半へ、という1年は「見逃した」という感じがしてくるのです。大人の1年は、どうということもないけど、その子たちの、いちばん可愛い、成長の時期を、見逃してしまったのが、この一年の唯一に残念なことでした。