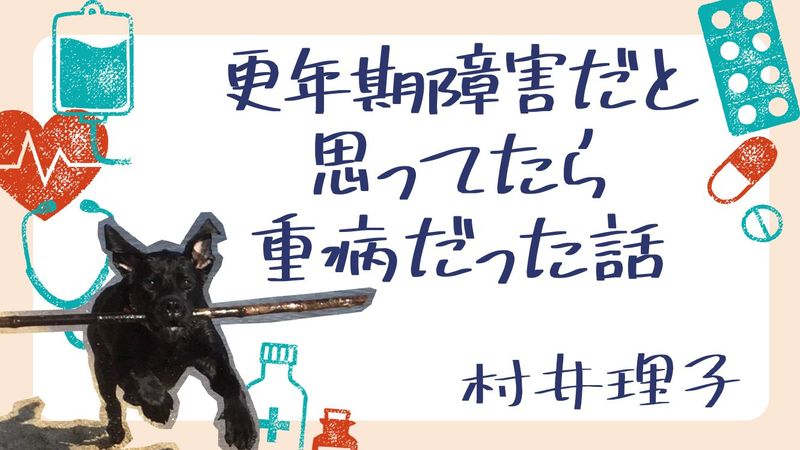「何もかも更年期障害だと片付けるなんて、自分に対するとんでもないネグレクトだ」。47歳の時に身体に起きた異変。のんきに構えていた村井さんだが、次第に事態は深刻になっていって……。『兄の終い』の著者が送る闘病エッセイ
単調で地味な私の人生に、大事件が起きた
私は琵琶湖のほとりで家族と暮らしながら、細々と翻訳業を営む、どこにでもいる普通の女だ。先日、50歳になった。家族は54歳の夫と14歳の双子の息子、そして3歳のラブラドール・レトリバーのハリーである。家から車で20分ほどの距離に夫の両親が住んでいる。2人とも80歳を過ぎた後期高齢者で、そろそろ誰かの手を借りなければ日常生活を営むのに支障が出はじめたという状況だ。その誰かの手というのは、私の手の場合が多いのが、昨今の悩みである。
毎朝、夫や子どもたちがそれぞれ向かうべき場所に行ったあと、キッチンのすぐ横にある作り付けのテーブルに座って、翻訳作業をしている。大きなモニタ2台とプリンタ、出版社から次々と届く書籍が積み上げられた狭いテーブルは、キーボードぐらいしか置くスペースがないほどの状況だ。私のこの小さな職場を見る人の多くが絶句し、「こんなに狭い場所で作業してるんですか!」と呆れるのだが、私にとっては快適な作業場である。なにせ、夕飯の支度や洗濯をしながら、いくらでも仕事ができる。わが家の家事は、何もかもが同時進行で行われる。私の頭のなかで、その作業工程はしっかり順序立てられ、連日、決まり切った形で粛々と行われている。
翻訳家と聞くとなにやらすごくかっこいいイメージがあるようなのだが、実際のところ、やっている作業は地味そのものだ。一行ずつ、読んでは日本語に直していく、そんな作業の繰り返しだ。ただそれだけのことなのだけれど、結構難しい。難しいうえに地味。修行みたいだ。そのうえ、長丁場だ。ときどき、辞めたくなる。訳者は裏方の人間なので作業が地味なのは当然とも言えるのだが、世の中の翻訳家に対する華やかなイメージとかけ離れているようで申し訳ない限りだ。翻訳以外ではエッセイも書いているが(この文章だってそんなエッセイの一編です、一応)、こちらの作業は、より一層地味だ。たったひとり、静かに考え、文章に起こしていく。ただ、それだけ。地味。私の人生そのもののように思える。
そんな、単調で地味な私の人生に、大事件が起きたのは2年半前のことだ。突然、倒れてしまった。倒れたと言っても、バタリとどこかで倒れたというのではなく、体調が急激に悪化し駆け込んだ病院で、緊急入院を言い渡されたのだ。前兆がなかったのかとよく聞かれるのだけれど、実は、そこまではっきりとわかるような症状はなかった。主治医は、「これだけ悪かったらさすがに気づくはずなんですが、長年不調が続くとそれに体も心も慣れてしまい、気づきにくくなるということもあります」と、半分あきれ顔で言ってはいた。ちょっと疲れが出やすい。少し息が切れる。なんだか夜中に何度も起きる。不安で眠れない日が続く……思い当たるのは、これぐらいの症状だった。