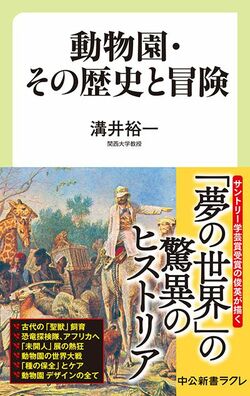これらは所有者の富や権力をアピールするための施設だったが、このように「支配」を前提にした動物飼育は、20世紀後半になるとしだいに批判されるようになっていく。動物は、はたして人間が思うままにしてよい存在なのか。彼らにも、最低限の権利はあるのではないか。
これがやがて、動物園に「動物保全センター」へ変容することや、自然環境をシミュレートした展示をおこなうよう、うながすようになるのだが、ひとは動物たちとともにいかに生きるべきかという問題は、『ジュラシック・ワールド』においても再三あらわれる。動物園は、まさにいまホットなテーマなのだ。
ジャルダン・デ・プラント――世界初の動物園
では、本格的な「動物園」が誕生したのはいつのことだろうか?
動物園史家ヴァーノン・N・キスリング・ジュニアの定義によれば、動物園とは、研究や一般人への教育、保全を目的に野生動物を飼うところである。たしかにそのとおりだが、これからみていくように、動物園をめぐる文化はその枠内におさまるわけではない。動物園は、近世のメナジェリー(動物コレクションの呼称)の性質を受けついでいた。たとえば、動物園は珍種をかき集めることで、祖国の軍事的・外交的・経済的な力をみせびらかすところとして機能したし、動物芸などの娯楽にも傾きがちであった。だが動物園はそこから、異国の自然や文化を「体験」するための場にもなっていく。
世界初の動物園とされるのはパリの「ジャルダン・デ・プラント」である。これが誕生したきっかけはフランス革命(1789~99)だった。かつてヴェルサイユ宮殿に、王による支配の象徴としてメナジェリーがあった。だが革命のさなか、ルイ16世がパリにむりやり移住させられたあと(彼と王妃はのちに処刑される)、動物たちは毛皮をはぐために拉致されるなどして、数を減らしていた。残ったものも、パリの王立薬草園(ジャルダン・ロワイヤル・デ・プラント・メディシナル)に送って、標本にして「人びとの教育に役だてる」のはどうかということになった。