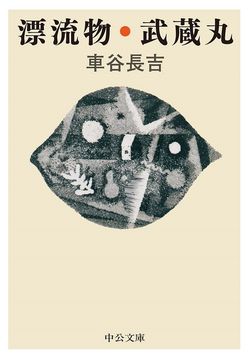強迫神経症で一日に何十回も手を洗うように
「文士じゃなくて、弁士でもメシが喰える」と冷やかされるくらい、連れ合いは雄弁である。「一口三十分」といわれる。同じ内容であっても、時と場合によって、順序を入れ替えたり、或る部分を抹消したり、付け加えたり、故意に変形したり、誇張したりして、聞くたびに色合いがちがうのを、はじめのころは私は驚き、咎めた。
「あなたは嘘つきだ、職業病だ」と、なじったが、このごろは、あ、また話を作っている、と聞くようになった。すると気持が楽になった。いま考えると、それは私たちが直面した危機を乗り越える手段でもあった。
その危機とは結婚2年4ヵ月めの春、連れ合いの強迫神経症の発病であった。因業が表看板になっている男だが、因業であることを持続させる意志の力は、しばしばこの人の肉体の力を凌駕するほどである。因業の刃がただ空を斬るということはなくて、さまざまな抵抗にあう。それに堪えようとすることで、心身を擦り減らし、消耗する。自分をもてあます。強迫神経症の発病は、目先の失業だけが原因ではなかった。
幻覚と幻聴、幻視に悩まされ、一日に何十回も手を洗い清め、私の立ち居振る舞いを規制するようになった。日常の暮らしをそのまま書くことが、とくに操作もせずに非日常の詩になってしまう経験を私はした。(それが詩集『時の雨』となって結実した。)
すると、この暮らしは虚構なんだ、嘘なんだ、というめまいのような感覚がやってきた。嘘をつくことを許容しはじめたのは、その感覚を味わってからだった。連れ合いは自分の病状を私に語り、私はひと月ほどはすべての仕事を放擲し、それに耳を傾け、理解しようとした。
この病気の出口はじつはまだ見つかっていないのだが、徐々に恢復に向かっていることは確かである。