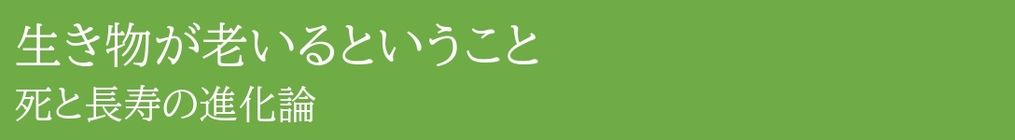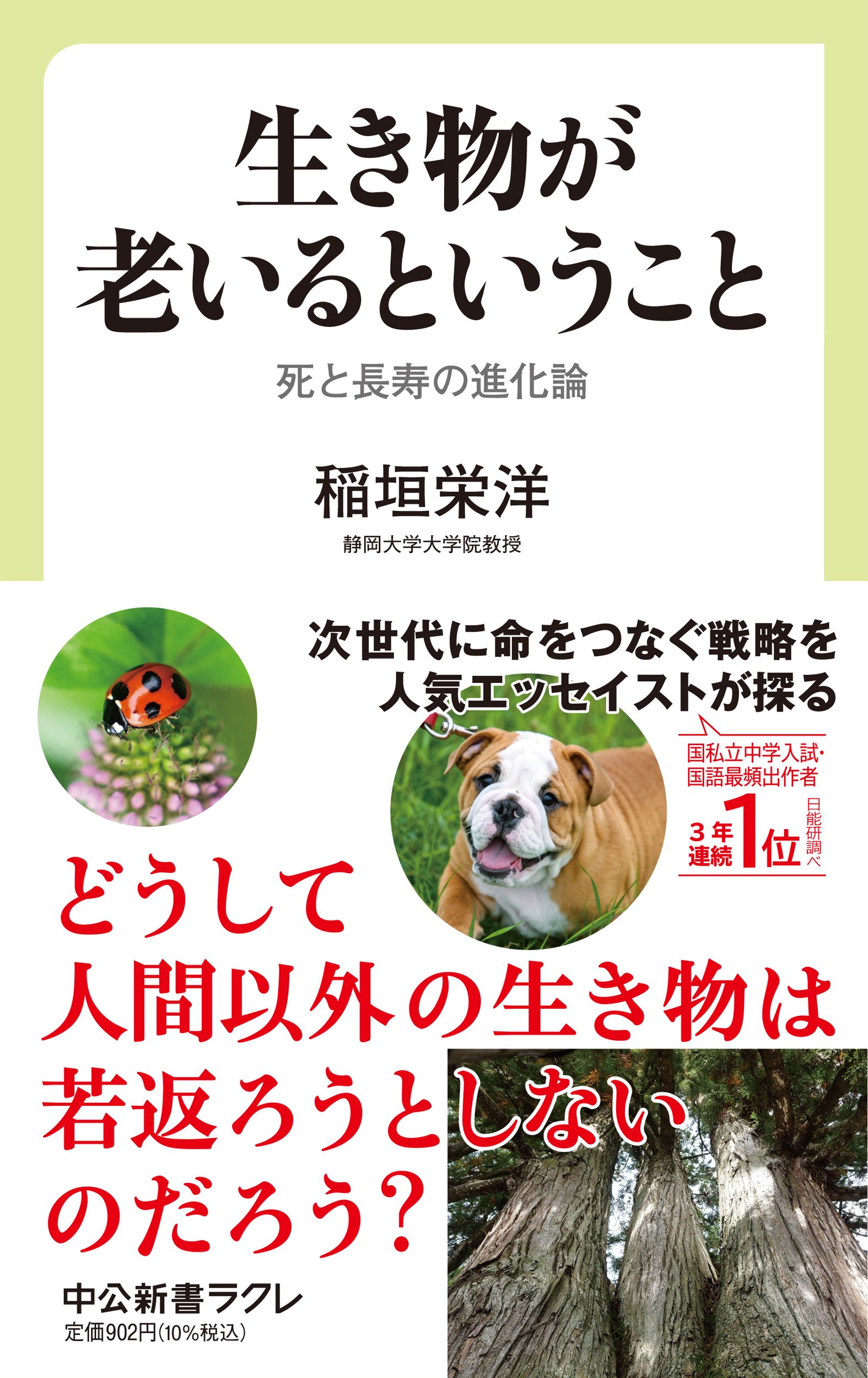「鶴は千年、亀は万年」その続きとは
老いることなく、そのままツルに変身しても良さそうなものだが、浦島太郎は、一度、老人の姿になった。老いることは、高貴なツルになるために必要なステージだったのだ。そして、老いた先に幸せがあったのである。
老いることもなく、死ぬこともなく、若いまま生き続けることは、けっして幸せではなかったのだ。
江戸時代の禅僧である仙厓義梵(せんがいぎぼん)は、「鶴は千年、亀は万年」に続けて、「我は天年」と付け加えたという。
「千年も万年も生きることはできないが、ただ与えられた命を全うする」と言ったのである。示唆に富む言葉である。
※本稿は、『生き物が老いるということ――死と長寿の進化論』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
『生き物が老いるということ――死と長寿の進化論』好評発売中です
どうして人間以外の生き物は若返ろうとしないのだろう?
イネにとって老いはまさに米を実らせる、もっとも輝きを持つステージである。人間はどうして実りに目をむけず、いつまでも青々としていようとするのか。実は老いは生物が進化の歴史の中で磨いてきた戦略なのだ。次世代へと命をつなぎながら、私たちの体は老いていくのである。人類はけっして強い生物ではないが、助け合い、そして年寄りの知恵を活かすことによって「長生き」を手に入れたのだ。老化という最強戦略の秘密に迫る。
「国私立中学入試・国語 最頻出作者」3年連続1位(日能研調べ)