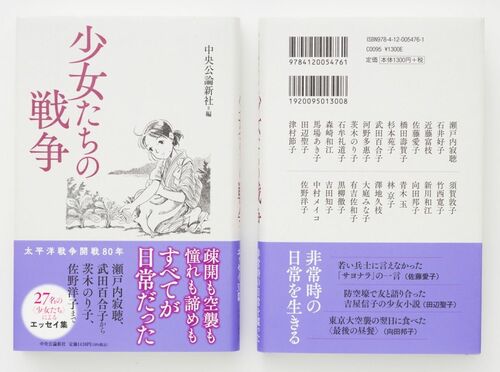青春の真っただなかで迎えた終戦
また終戦記念日がめぐってくる。あれから39年もたって、随分いろんなことを忘れてしまったけれど、終戦の日と、その前後のことは、今でも鮮明によみがえってくる。日本人の誰もがそうであったように、私にも私の人生を変える最も烈(はげ)しい運命の転機だったからであろう。昭和20〔1945〕年、私は二十(はたち)、青春の真っただなかで迎えた終戦であった。
当時、日本女子大の3年だった私は、東京の学校も空襲で閉鎖され、その年の3月ごろから大阪へ帰って、海軍経理部へ勤めていた。母の暮らす堺市とは大分離れた、宝塚に近いところにあったので、母とは別れての下宿暮らしであった。
そのころ、大阪周辺でも毎日のように空襲があり、経理部でも防空壕へ避難する間に、何度機銃掃射にあったか知れない。夜は、必ずどこかで火の手があがり、その度に町や都市が焼土(しょうど)と化していく。
7月のなかばに、下宿の2階から夜空を焦がす炎が、ひときわ烈しく眺められた。堺市が空襲を受けているらしいという情報に、思わず息をのんだ。堺市には、母がひとりで暮らしている家があった。が、勿論(もちろん)助けにいくことも出来ない。夜通し震えながら、ただ真っ赤な空を見つめているだけであった。
夜があけて、事情を察した上司が、様子を見にゆく車を出して下さったが、とても熱くて町の中へは入れない。見渡す限りの焼け野原には、黒焦げの死体が至るところに転がり、電車の高架線の鉄塔には、自転車やトタン板などがからまりついていて、熱風の恐ろしさに身の毛がよだった。
父は、京城(今のソウル)で事業をしていて、当時もう連絡も途絶え、母には疎開をすすめていたが、留守を守るもののつとめだと、堺の家を動こうとはしなかった。その母のいる家の辺りは、防空壕の中まで火が入り、死体が折り重なっていると知らされ、母のことは諦めて引き返した。