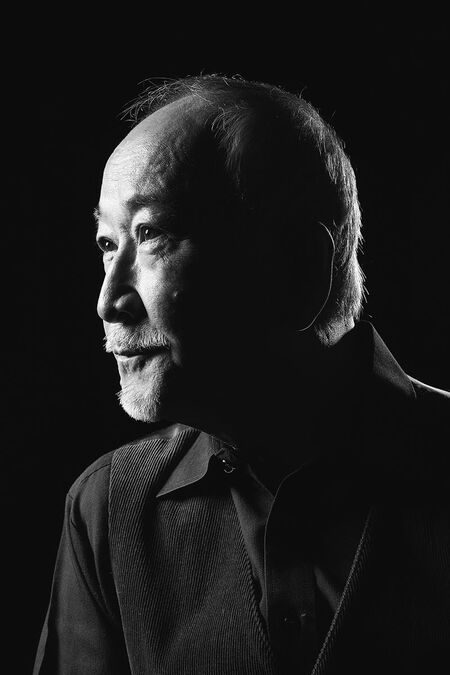大反対していた親父とお袋が
なつかしい「ベニサン・ピット」。よく通ったものだった。TPTとは、93年春に隅田川左岸のこの劇場をホームグラウンドに、イギリスの演出家デヴィッド・ルヴォーとプロデューサーの門井均氏が立ち上げた、現代演劇の実験プロジェクト。
――僕は92年の『エリーダ~海の夫人~』から始まりましたが、TPTに入ったおかげで、芝居や戯曲の構造とか、演技のもっとも基礎にある考えを整理するのに、とても役立ちました。というのも、演出家が外国人だから、「ここでやりたいことは、こういうことなんだ」というのを自分の中でしっかり整理してから通訳に話さなきゃ意図がはっきり伝わらない。それが今の役作りでも習慣になっています。
ルヴォーさんの言葉で今も大事にしているのは、芝居というのは意思の働きかけ合いだということ。僕、とある新劇の舞台で、「木場さんの役目は、主役の女性の言葉を引き出すための触媒です」と言われたことがあって。ムカッとしました。作品のテーマありきで、役者は材料だというんですから。
でもルヴォーさんは、ある二人が言葉を交わすと、相手に意思を働きかけられたほうが、働きかけ返す。そこにドラマが生まれる。これができないなら戯曲は本で読めばいい、とよく言ってましたね。
だから僕は舞台の上で、なぜ自分がここにいるのか、なぜこの台詞を言うのか、自分なりの分析や解釈をもって臨んでいます。『三人姉妹』という舞台を最後に退団しましたが、今もその考え方は役立っています。
そういえば、TPTにいる間、親父やお袋が、よく観に来たんですよ。最初は「役者なんてやくざな商売だ」って大反対したくせに。劇場のあった江東区森下は実家のすぐ近くで、親父はうなぎ屋で一杯飲んでから来るんです。
『テレーズ・ラカン』で藤真利子が裸になった時、客席から「ウォー」って声がして、見たらうちの親父だった(笑)。お袋も近所の友だちと来て、「ここで泣けるのよ」なんて解説してました。嬉しかったみたいですよ。その時は恥ずかしかったですけど、親ってありがたいものですね。